1.リミナルスペースに表れる概念
昨年から、特に海外のサブカルチャーとして、「リミナル・スペース」というのがひそかに流行しているという。これは、例えば、駅構内の地下道、駐車場のスペースの一角、もしくは、打ち捨てられた廃墟じみた建物の一角など、本来、無機質な建築の空間に奇妙な魅惑を見出すというものである。
いくらかニッチな趣味ではあるものの、こういった空間に、写真愛好家の人々がフォーカスを当て、それを被写体として収める文化的な活動がひそかに愛好家の間で流行っているのだという。このいうなれば、ニッチな趣味「リミナル・スペース」は、海外版2ちゃんねるの「4chan」で最初に取りざたされたもので、じわじわと海外の愛好家たちの間で親しまれている趣味なのだそうだ。
一時期、廃墟探索というのが、日本でもサブカルの領域ではあるけれども、ひそかに愛好家たちの間で取りざたされていたわけだし、「廃墟」というテーマを掲げた写真集も各出版社から刊行されていたのを思い出す。
これも、上記のリミナルスペースと同様、既に閉園した遊園地、長らく打ち捨てられ、所有権利者も解体費用を捻出するのを諦めた小大の工業施設、あるいは商業施設の景観にノスタルジアを見出すというものである。
確かにそういった現代の遺構のような建築物は、その虚ろな空間に接した際に郷愁にも似た感覚を覚えることがある。なんだか不気味のようにも思える空虚な空間に不思議な感覚を見出す、それはいわく言い難い、安らぎとか落ち着きにも近い奇妙な感覚である。我々が、なぜ、そういった本来、社会生産から切り離され、本来の役割を失った建築物に、そういった安らぎにも似た感覚を覚えるのかといえば、それはある種の無機物が目の前に明瞭に存在することを確認することにより、それと対比的に、自己という実在性を強めるからにほかならない。
廃墟、古い遺構、人気のない工業施設の一角は、その対象物そのものは生きているという感覚からは程遠い、だから、我々はその対象物と接した際に、謂わば、それと対比的に自分が生きているという感覚が鋭くなり、自己の実在性が強められ、その思いをじっくり噛みしめさえする。さながら、現実と異次元の狭間が目の前に不意に生じたかのような錯覚を、カメラのレンズを向ける人たち、また、その場にたたずんでいる人は見いださずにはいられないのである。
つまり、定義としていえば、リミナル・スペースとは、当たり前の日常の現実空間の中に生じた奇妙な異空間ともいえる。そして、これはどちらかといえば、たとえば、工業施設のような人工的な建築物中に、こういった概念が見出される場合が多い。つい昨日までごく当たり前に目の前に存在していたなんでもないような空間、それは昨日までは、面白みのない無機質な空間という印象だったかもしれない。しかし、今日それに接した際にまるでその対象物の印象が変わり、ミステリアスな異空間が眼の前に広がっている事実を我々は発見するのである。
2.パンデミックがもたらした異空間
2020年からの世界的なパンデミックは、世界各地にこういった「リミナルスベース」を生じさせた。それがむしろ商業生産の盛んな先進国であればあるほど、こういった奇妙な異空間が至る場所に生じることになった。
感染者数の増大により、多くの先進国の政府は、本来の社会生産活動を制限し、一般市民を家の中にとどまるように促した。そして、感染者数の増大に歯止めをかけようと試みた。それらのことがどのような社会的作用をもたらしたのかといえば、むしろ経済活動の停止に依る人類の進化の鈍化であった。人々は、停滞し、その場に留まることにより、20世紀からすすめてきた資本主義という手法を今一度見直さねばならなくなった。社会的な議論が世界各地で熱心になされた、生産活動に舵取りをするべきか、はたまた人間の生活安全を取るべきか。様々な活発な議論がインターネットでも交わされた。しかし、もっともらしい結論はいまだ出ていない。すべての国家、政府は、これらの2つの概念を天秤にかけ、バランスというか均衡を保ちながら、政策を打ち出し、そして市民の信頼を獲得しようとしている。それは現在の2022年においても変わらない。政府は国民の顔色を伺いながら、のらりくらりと政治を行っている。
そして、この2020年に起こったパンデミックという出来事は、一般市民に与えた影響にとどまらず、街の景観の変化にも顕著に顕れた。あらためて思い出してみていただきたいのは、我々が日頃当たり前に見ていた社会的な空間中に何の前触れもなく突如として空白が生じ、そこに、いわば「リミナル・スペース」と呼ばれる異空間が生じたのだ。営業の自粛を迫られ人気のとだえた所業施設、それまで、客がビールジョッキを片手に賑わっていた居酒屋ののれんじまい、また、それまで数多くの人々がすれ違っていた駅前通りの水を打ったかのような閑散、都道府県を跨ぐことを禁止された結果として生じた多くの車の通行を失った国道、それから、殷賑をきわめていた何らかの市場や商店街のような空間に、一種の不可思議な空隙が生じた。また、今、一度考えてみてほしい、これらの無数の空間に当たり前に存在していた多くの人たちの消失、そこには、突如として、これまでに存在した現実空間の中に、不可思議な異空間、リミナル・スペースが生じたように、多くの人々は感じたにちがいないのである。
2020年、東京でも緊急事態宣言が発令されたが、それは少なくとも大都市圏だけではなく、いくらか私の住んでいる郊外にも少なからずの影響を与え、「異空間」、言いかえればリミナルスペースが生じた。今では、そういった発令がなされたとしても、多くの人は日常活動くらいは普通に行うと思われるが、このパンデミックが始まった時はそうではなかったのだ。人々は目に見えないウイルスの影におびえ、日々接する情報をそれらにしぼっていったのである。
2020年の当初、多くの人々がこの出来事がなぜ起こったのかも理解できず、さらにどういったことが起こっているのかも見分けづらくなっていた。ここで、後世の人類のための情報として伝えておきたいのは、この時、我々は目の前におこっている現象よりも、あるていどインターネットやテレビを介して提供される、なんらかの情報、なんらかの報道を通じて出来事に対する理解を深め、目の前に起こっている現象に対処していく以外の方法はほとんどなかった。このことは、それまでの社会の様相を一変させた。つまり、2019年以前と2020年以後の世界はまるきり一変してしまったのだ。
たとえば、もし、この目に見えないウイルスの脅威に怯えを覚えていた人にとっては、外出を自発的に諦めるという行動の選択にもつながった。報道では率先してショッキングな映像が選ばれ、それはたとえば最初の武漢市場の奇妙な映像に象徴的にあらわれていた。あの時、今でも思い出すのだが、私が非日常の日常の中でつくづく感じ、恐怖すらおぼえ、一番おそれたのは、ウイルスの存在ではなかった。それは、これまで当たり前であった日常の平穏が脅かされるのではないかという感覚、どうあっても変化を余儀なくされることに対する異質な恐れ、それはまた現実空間でいうなら、日常の空間の中に不意に生じた奇妙な「リミナル・スペース」を意味したのだ。
日常的に生きている当たり前の空間がおびやかされ、そこには、「AKIRA」、または「新世紀エヴァンゲリオン」に登場するような不思議なSFチックな空間が生じ、バス停の電光掲示板に映っていた緊急自体宣言発令の文字、あるいは、外出をお控えくださいといった奇妙なデジタルの文字群が不意をついて眼の前に立ち上ってきた。
その時、何らかの不思議な感覚をおぼえ、これは現実に起こったことなのだろうかとも考えた。今、なんとなく思い返すのは、あのとき、私は、現実空間に居ながら、ある種の異空間にやってきたようないいしれない実感をおぼえていた。それは、見渡すかぎりいちめん、本来の生産活動、経済活動の気配が途絶え、2019年以前の世界の空気感を失い、巨大なリミナルスペースに身をおいたか、迷い込んだかのような錯覚に陥った。いや、そうあらざるをえなかったのだ。
3.リミナル・スペースの探索
2021年あたりから、2ちゃんねるの海外版「4 chan」で、これらのリミナルスペースという概念が話題に上がるようになった。
2021年になると、その前年とはまるで世界の様相が変わり、表向きには生産活動や経済活動にシフトチェンジを図るようになった。内向きな方向性から外向きな方向性にいわばベクトルを転じたことは、社会構造として健全といえるかもしれないが、また、一方で社会内に生きている一般市民の心を置き去りにしたともいえる。人々は、2019年のロックダウンに生じた空白のようなものを脳裏から拭い去ることは出来なかった。その中で、直接的な因果関係を結びつけるのは少し暴論なのかもしれないが、この「リミナル・スペース」という新たな2020年代の概念が出てきた。人々は、あらためて、日常化した商業施設、工業施設内の異空間を探し求める。それは、一種の2019年に起きた出来事を再認識するようなものといえるかもしれない。
この「リミナルスペース」は、そもそも人類学者ターナーによって提言された言葉であるらしく、「日常生活の規範から逸脱し,境界状態にある人間の不確定な状況をさす言葉」である。さらに言えば、このリミナルスペースは「Threshold」を語源に持ち、感覚的なニュアンスを交えて、海外の人はこの言葉、概念を使用するようになっている。また、このスレッショルドという語は、「閾値」を意味し、音楽のリミックス、特にマスタリング作業の段階で使われる要素で、「スレッショルド」という値を増減させることによって音のコンプレッション、圧縮率を調整し、作品として再生されたときの音の圧縮率、音圧をコントロールするのである。
ある人は、「リミナル・スペース」、現実の空間に生じた異空間を五感、またはそれ以上の感覚で捉え、それにあきたらない人は、カメラを介し被写体としておさめ、認識下にある数値化できないそれぞれの閾値を用いて現実性をコントロールしようとする。
もちろん、言うまでもなく、それらの景物に建築学における配列、規則性、黄金比といった興味を、その中に見出す人も少なからず存在するものと思われるが、それよりも、昨年からこの概念が趣味として、海外のファンの間で広がりを見せるようになったのは、近年の世界の劇的な変化、世相のようなものを反映しているようにも思える。
リミナルスペースと呼ばれる異質な空間、人々はその中に、いくらかの恐れや不安とともに反面、奇妙なノスタルジア、安らぎを見出す。
それは先述したように、自分が現在、今という瞬間に生きていることを対比的に確認するための認識作業ともいえる。リミナルスペースは、一般的なカルチャーとは呼べないものの、特に、今日の社会、世界情勢を見渡した時、何らかの重要なテーマが反映されているように思えてならない。こういった概念に興味を抱くのは、多くの人々が、日々生きる現実の中に「異空間」を見出しているからにほかならない。今後の世界がどう進展していくかはわからない。いずれにせよ、いまだ2022年の人類は、リミナルスペースと呼ばれる現実空間と異空間の狭間をあてどなく彷徨いつづけているのだ。





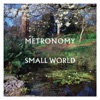













.jpg)













