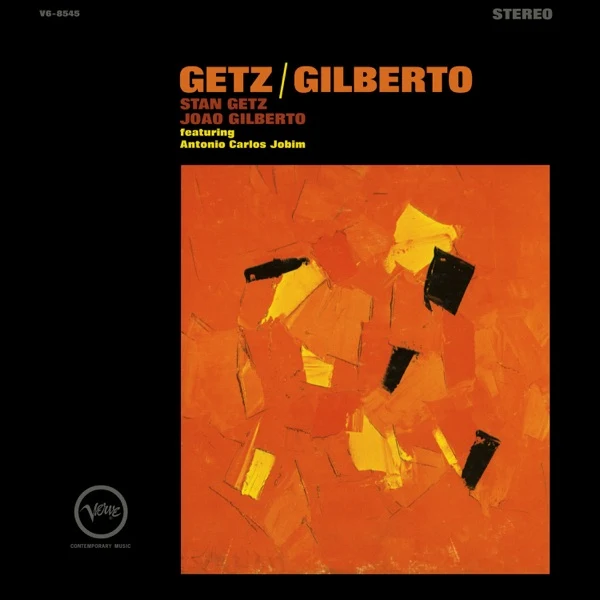”クンビア”はラテンアメリカのダンス音楽の一つで、コロンビアの伝統音楽でもある。この伝統音楽はおよそ1800年頃には存在したと言われ、1960年代に人気が沸騰し、世界中で人気を博した。
この音楽が近隣諸国に伝播していくにつれ、アスカンビア・ペルアナ(ペルー)、クンビア、アルゼンチン(アルゼンチン)、クンビア・チレナ(チリ)、クンビア・メキシカナ(メキシコ)など、各諸国で新しい形態のクンビアの派生音楽を生み出すことになった。メキシカーナなど上記の派生した音楽にも心を惹かれるものがありますが、特にコロンビアの海岸地域で発生した伝統的なクンビア、その音楽の最初期の発展こそがコロンビアという国家の重要な文化の基礎を形成している。
クンビアにはその前身となる音楽のスタイルがあるらしく、フォルクロルコロンビアーノといわれるアフリカ系コロンビア人が植民地時代に大陸から持ち寄った民族音楽がその発祥とされています。
植民地化以降、コロンビアの沿岸地域には、スペイン人、ネイティヴのコロンビア人、アフリカ系のコロンビア人が混在して生活していたと言われている。それらの人種的な混在が多様な音楽のスタイルを生み出し、何世紀にわたる音楽文化の礎石を築き上げていった。そして、この音楽は、移民としてアフリカ大陸から渡来した人々の音楽の記憶の継承でもある。 時々、遊牧民やジプシー等の民族をはじめとする人々は、定住する土地を持たぬため、音楽やそれにまつわるダンス、あるいは物語という形によって以降の人々に記憶を継承していくのである。
”クンビア”はコロンビアの伝統的な民俗音楽ーFolkーとして知られている。日頃、わたしたちがよく使用する”フォーク音楽”というのは、民俗音楽を指し示し、それは以前の時代の一地域に生きていた誰かの記憶や行動形式、あるいは生活規範であったり思想形態の継承を意味します。それは旋律やリズム、そして、スケールなどを単に模倣したり、なぞらえたりするのではなく、誰かの口伝によって次の世代に伝えられていく物語と同様に、次の世代に向けての文化継承の意味が込められている。 それは、写真や映像のように形あるアーカイブとして保存できぬために、歴史的にとても意義深いものなのでしょう。他地域のフォーク音楽の起源や発展の経緯が深い靄の中にあるのと同じく、クンビアという伝統音楽の出発については明らかになっていません。
例えば、コロンビアのミュージシャンで、ギジェルモ・カルボ・オリベラ、ギジェルモ・アバディア・モラレスなどの民俗学者や音楽学者は、クンビアがバントゥー語の「Kumbe」に由来すると指摘している。この語源は踊る(kumbe)という意味があると両氏は言う。また、2006年になって、同国の音楽学者でミュージシャンのギジェルモ・カルボ・ロンデロスはクンビアについて、「議論の余地がある」としている。少なくとも同氏は、この音楽が「cumbe」という語に由来すると指摘している。
''クンベ''は赤道ギニアのダンス形式がその前身とされる。現在のマグダレナ川地域の上流渓谷の先住民族が住む地域、”ポカブイ”という場所に最初に出現したと現地の人々は信じている。
該当する音楽を聴けばお分かりのように、クンビアは、スペインのサルサの音楽的な気風に近い。情熱があり、陽気で、反復的なリズムや歌を通じて、舞踊音楽の一つの重要な特性である強固なエネルギーを外側に放つ。また、それらが世界各地のカーニバルのように、多くの人で演奏されたり、踊られるものとあれば、その意味は一層強まる。つまり、クンビアがラテンアメリカの舞踊音楽として発展していったことは、民俗学の観点から見ると、ブラジルのサンバ、スペインのサルサと同じような音楽的な動機があるのではないかと推測出来るわけです。
 |
文化というのは、単一民族の行動形式や思想形態の伝承から成り立つことはきわめて少ない。これは、神聖ローマ帝国や、スペイン帝国、オスマン・トルコ帝国、大英帝国、アメリカというように、世界の中心地が何世紀にわたって絶えず塗り替えられてきた歴史の変遷を見ると明らかである。つまり、現代的な政治学における移民という考えと切り離してみても、オセアニアの歴史は土地に住む民族が世紀毎に変遷し、それらの異文化が混淆を重ねながら、新しい伝統形式が積み上げられていった。ラテンアメリカの一地域であるコロンビアという土地も同じでしょう。この地域はとりわけスペインやその国境を接するフランスからの影響が強く、クンビアの演奏時に着用される民族衣装は、スペインとチロル地方の服飾の影響がどこかに見受けられる。それらにアフリカの大胆な原色を中心とした色合いを加えたのが、クンビアの衣装なのです。
また、ヨーロッパからの文化的な影響の他に、リズムやビート、実際に使用される楽器を見ると、アフリカの儀式音楽の影響が含まれている。また、ガイタ、カニャデミロという楽器を演奏する点を見ると、コロンビアの先住民族の音楽の影響もあるという指摘もある。これらの複数の地域の音楽や文化のフュージョン性は異質な音響、音楽におけるエキゾチックな気風を生み出す。その中にはアフロ・ビートやアフロ・ジャズの原始的なリズムの継承性もあるが、一方で、ラテンアメリカの音楽的な陽気さもまた、この舞踏音楽の重要な礎となっているのです。
このジャンルの音楽的な特徴は、2/4、4/4というシンプルなリズム性に求められる。これらはアフリカの音楽からの影響もあるかもしれないが、リズムそのものを簡素化して踊りのための音楽として洗練させたのでしょうか。しかし、クンビアのリズムにはサンバやサルサに引けを取らない迫力があり、原始的な質感を持つパーカッションによるリズムがこの音楽の最大の魅力になっていることがわかる。当初、クンビアは、ボーカルなしの器楽曲として始まったが、他の地域のフォーク音楽と同じように、叙情的な詩がスケールとリズムに追加されることに。そして、演奏者たちはさまざまな変奏や工夫を重ね、楽器を増やしたりすることで、この音楽を発展させていった。
また、伝聞するところによれば、クンビアには男女間のシンプルな情愛が踊りと音楽によって表現される。これは実際のダンスのなかで、男女がペアで踊るというフラメンコと同じような様式にその概念が込められている。ダンス全体の動きを通して、男性は女性の体を自分の方に引き寄せる。またクンビアの女性ダンサーはサンバのように派手な衣装を身にまとうのが一般的であり、スパンコール、花の頭冠、そしてイヤリング、長いスカートを身につける。これらは、スペインやアルゼンチン、ブラジル等の服飾的な影響が込められているようです。他方、男性の衣装はコロンビアの性質が強く、ソンブレロ、白いズボン、白いシャツ、赤いバンダナというように扇情的な色合いの民族衣装を身に纏う。演奏者は踊りを通じ、民族的な歴史を表現し、アフリカとスペイン、そしてコロンビアの先住民族へのリスペクトを織り交ぜているようです。