東京・原宿を拠点とするオークションハウス NEW AUCTIONは、2025年2月1日(土)に第8回目となる公開型オークション「NEW 008」を開催いたします。
この度は、マリリン・ミンターの「Up Close」と題された写真シリーズや、ヨハネス・イッテンのコラージュ、ルース・ルートのアルミニウムの上に重ねられた大胆な色彩の作品など形と色の関係に特徴のある作家、もの派の菅 木志雄や小清水 漸 、高松 次郎 のシャドーシリーズなど時代や表現方法を超えた様々な作品が取り揃いました。
今回ご紹介できる作品は、すでに作者の手を離れたものなので、それぞれの作品にどのような意図がありどのような想いで制作されたのか全てをお伝えする事ができませんができる限り作品の魅力が伝わるようにラインナップを組みました。静かに作品の声に耳を傾けながら、想像を膨らませていくことは何ものにも変えられない喜びです。是非この機会にご鑑賞いただけましたら幸いです。
渋谷MIYASHITA PARKにある「SAI」にて開催されるオークションプレビューでは、全ての出品作品を実際にご鑑賞いただけます。 また、今回のオークションは、プレビューと同じく「SAI」にて開催いたします。皆様のご来場、ご参加を心よりお待ち申し上げております。
●主な出品作品
Joseph Beuys(ヨーゼフ・ボイス)/ Mike Kelley(マイク・ケリー)/ Marilyn Minter(マリリン・ミンター)/ Johannes Itten(ヨハネス・イッテン)/ Edward Ruscha(エド・ルシェ)/ Ellsworth KELLY(エルズワース・ケリー)/ Robert Mapplethorpe(ロバート・メイプルソープ)/ Austin Lee(オースティン・リー)/ 高松 次郎/ 井上 有一/ 奈良 美智 / 宮島 達男 / 土屋 仁応 / 岡崎 和郎 / 今井 麗 /友沢 こたお / 上田 義彦 / 小清水 漸 etc...
●オークション情報
「NEW 008」
プレビュー
会期:2025年1月25日(土) - 1月31日(金)
時間:11:00 - 20:00
(最終日のみ17:00まで)
会場:SAI
住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-20-10RAYARD MIYASHITA PARK South 3F
オークション
会期:2025年2月1日(土)
時間:START 13:00 -(OPEN 12:30-)
会場:SAI
住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-20-10RAYARD MIYASHITA PARK South 3F
 |
| TAKAMATSU Jiro, ブラシの影 No.182, 1967, oil on wood, wall hook |
1960年代に「山手線事件」(1962年)や「首都圏清掃整理促進運動」(1964年)など、芸術を通して社会に対する「直接行動」を体現した前衛芸術集団ハイレッドセンターのメンバーの一人として広く知られる高松 次郎(1936-1998)。
個人名義で制作活動をしてきた高松は、絵画や立体作品、版画や写真など多岐にわたる媒体で作品を発表してきた。その作風には、存在といった全体像を捉えることが難しい〈空虚を充満した事物〉に対して徹底的な問いかけを行ってきた主知性のある姿勢が一貫して強く見受けられる。
高松は、1964年より「不在/存在」をテーマに〈影〉シリーズを作り始める。本作品《ブラシの影 No.182》は1967年に制作された絵画である。表面に取り付けられた実物のフックから伸びるようにブラシの影のみが描写されている。
2つの光源により壁に映し出された画面上には存在しないブラシの影をキャンヴァスへと描写することで、実在そのものを見なくとも2次元の影からその姿を想起させる。「見ることの曖昧さ」を逆手にとることで、実在に対する不信感を問いかけるのである。
 |
| KOSHIMIZU Susumu, レリーフ ‘91-17, 1991, pigment on carved wood panel |
戦後華々しい高度経済成長を遂げた日本産業であったが、その一方で、1960 年代には大気汚染や水質汚染といった公害が影を落としていた。
〈モノ派〉は、そんな西洋主義的成長へと傾倒していく時流に対し疑問を呈するかのように、未加工の物質や物体を主役として作中に登場させることで、モノを越えたところに潜む存在の開示を追求した芸術傾向である。関根 伸夫の《位相 - 大地》(1968 年)を契機に、当時の多摩美術大学の学生数名と李禹煥らを巻き込みながら、各々の芸術実践を通して展開されていった。
当時、多摩美術大学彫刻科の学生であり、同現象を起こした主要メンバーの一人であった小清水 漸(1944-)も、関根の《位相 - 大地》に触発されるかのように、日本文化固有の自然観を根底に、木や石、紙、土、鉄といった素材との協働関係を通して、創作行為を行なっていく。
また、人間の自然的性質(素材との関わり方)へと着目し、鉄であれば磨く、木であれば削るといった加工方法を通してその関係性を露出させる。しかし、その加工前と後を経ても、素材であるモノの本質はなんら変わりはないのである。その代表的な作品には、《垂線》(1969 年)、《かみ》(1969 年)、《鉄 I》(1970 年)、〈表面から表面へ〉シリーズなどがある。
本作品《レリーフ ʻ91-17》は、小清水が 70 年代後期より取り組み始めた木彫レリーフシリーズの一環で、1991 年に制作された。木の表面に広がる筆の点をイメージさせる彫りと鮮やかな緑青の視覚的な盛り上がりを表現した塗りが施されている。
絵画にも彫刻にも定義されないミディアム上に、双方の加工方法を用いることで、視覚的遊びが取り入れられている。小清水は、素材の保持する不変的本質を明らかにすることで、自身が 70 年代より探究し続ける揺るぎない実践を顕現するのである。
 |
| TSUCHIYA Yoshimasa, 鵺, 2021, painted camphor wood, labradorite, with original box |
神奈川県に生まれた土屋仁応(1977-)は、東京藝術大学彫刻科を卒業後、同大学院で保存修復彫刻を学んだ。学生時代に拝んだ滋賀県渡岸寺の十一面観音に感銘を受け、仏像制作で目にあたる部分に水晶やガラスを嵌め込む〈玉眼〉の技法を用いて独自の木彫を展開していく。元来、玉眼に用いられる水晶は別の工人によって作られてきた。
土屋の木彫でも、目にあたる素材の制作は、ガラス作家の田中福男氏が担当する。伝統的な仏像とは対照的に、土屋の木彫は、形の持たない感情や想念といった存在を動物や幻獣といったシンボル的モチーフへと投影するかのように具現している。
本作品のモチーフである《鵺》は、日本に伝わる伝説上の妖怪を指す。『平家物語』にも登場し、仁平時代、天皇が不吉な黒い雲に怯えることから、源頼政に黒雲退治を命じたところ、中に怪しい姿を見つけ矢を放つと、猿の頭、狸の胴体、蛇の尾、虎の手足をした化け物が落ちてきた、という伝えが記録されている。
得体の知れない存在は、不吉や不安の象徴であった。本作は、2021 年に高島屋で開催された作家の個展「鵺ー土屋仁応展」の表題になった作品である。コロナ渦中に開催された同展は、未曾有の状況下で、目に見えない不安が姿形を宿したかのように時代を象徴している。
鵺のその静謐とした佇まいは、不安に怯える我々と対比するかのようであり、人智を超えた状況の中で、超自然的な〈カミ〉的存在を想定する人間的本質を示唆するのである。
 |
| Marilyn MINTER, Bad Habit, 2017, dye sublimation print |
ニューヨークを拠点とするアメリカのビジュアル・アーティスト、マリリン・ミンター(1948-)は、セクシュアリティとエロティシズムに焦点を当てた写真作品で広く知られている。ミンターは、セクシュアリティを取り入れた作品で当初から物議を醸しており、女性のセクシュアリティから目を背け避けるのではなく、むしろ擁護する姿勢を示してきた。彼女にとって、女性の快楽や欲望を探求することは、女性アーティストが求められるとされる芸術作品の枠組みに対する反抗だった。
2000年代には、ミンターの作品にグラマー要素が加わり、官能性がさらに顕著に表現されるようになる。作家は撮影後にデジタル加工を一切行わず、フィルムで撮影することでイメージの「生の部分」を残している。また、撮影後に写真をトリミングすることなく、綿密なイメージ構成を体現している。このように、細部に至るまで驚くほど注意を払うことで、人目を引く作品を創り出す。
本作品は、絵画シリーズと並行して制作されている写真シリーズ「Up Close」の一作である。本シリーズは2000年から始まり、ペディキュアで塗られた足先、布からはみ出した乳首、華やかに彩られたまぶたや唇など、性的魅力の細部を探求している。ミンターは、社会における男女間のセクシュアリティに対するダブルスタンダードを声高に批判しており、本作品のタイトル《Bad Habit》も、女性のセクシュアリティが男性のそれよりも二次的と見なされる問題を皮肉ったものだと考えられる。快楽は反抗の行為であり、こうした個人的な性的充足の瞬間こそ、女性が家父長制的な権威を覆す手段となり得るかもしれない。
●ABOUT NEW AUCTION
/ INTRODUCTION
2021年6月、東京の文化発信地である原宿を拠点に新たなアートオークションハウス「NEW AUCTION」がスタートしました。私たちは従来のアートオークションという枠組みに縛られることなく、新しい体験、新しい価値観を提供することを目的とし、オークションの可能性を、原宿から世界に向けて拡張していきます。
/APPROACH
NEW AUCTIONでは、またアートマーケットの持続的な循環を促すための「アーティスト還元金」 の仕組みを導入している日本唯一のオークションハウスになります。 ご落札された作品の著作権者に対してアーティスト還元金を独自にお支払いすることで、 NEW AUCTIONを通じた取引が少しでもアーティストの支援に繋がることを目指します。NEW AUCTIONでは、国内外の様々なコレクターやギャラリー、ディーラーと独自のネットワークを構築すると同時に ファッション、カルチャー、建築、食、インフルエンサーなど業界を超えたチームとの連携を積極的に取り入れ、作品を最大限にプロモーションいたします。















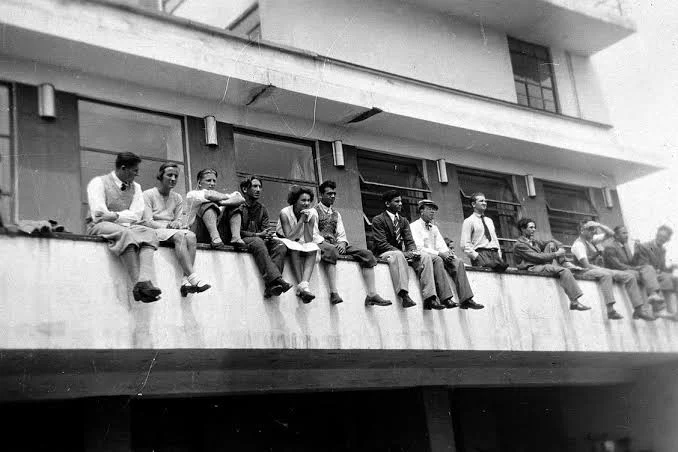






.jpg)














