Julianna Barwick
ジュリアナ・バーウィックは、アメリカ・ルイジアナ出身のアンビエントアーティスト。2006年から音楽家としての道のりを歩み、現在はLAを拠点に活動している。
ジュリアナ・バーウィックは、幼少期に過ごしたルイジアナの教会の聖歌隊への参加が自分の音楽的なルーツであると語っています。
ジュリアナ・バーウィックは、録音した自身のボーカルのサンプリングを幾層にもトラックメイクの段階でレイヤーとして重ね合わせることにより、ゴシック建築のような重厚な趣を持つ奥行きのある音響空間を生み出します。それは、ときに絵画のような色彩、また、教会建築そのもののような奥行きのある空間性を生み出し、聞き手を陶然とした心地に誘います。
ジュリアナ・バーウィックのミュージシャンとしてのキャリアの原点は、 2007年のデビュー・アルバム「Sanguine」に求められます。
この作品で、バーウィックはループステーションとループペダルを使用し、ヴォーカルのサンプリングとシンセサイザーのレイヤーをダブのような技法を用いて組み合わせることにより、立体的な構造を持つ、ヴォーカル曲とも電子音楽ともつかないような前衛的な作風を生み出している。2010年からは、レディオヘッドの「レコナー」のリミックスを手掛ける傍ら、共同作業を行うようになり、NYアンダーグランドシーンで活躍する森郁恵との作品「FRKWYS Vol.6:Juliana Barwick Ikue Mori」を発表しています。
最初のフルレングスアルバム「The Magic Place」は、最初にスタジオレコーディングが行われ、実際のピアノ演奏と、ヴォーカルのループを融合した叙情性あふれるアンビエント音楽を確立しています。この作品タイトルは、ジュリアナ・バーウィックの家庭の農場にあった一本の木に因んでいる。
2011年発表「Matrimony Remixes」では、ディプロ、ヘラルド・ネグロ、プリンス・ラマ、アリアス・ペイルをゲストに招いてリミックスを制作する。2012年、ヘラルド・ネグロとデュオ「Ombre」を結成、アルバム「Believe You Me」をリリースしています。
その後、2013年に二作目のオリジナル・アルバム「Nepenthe」を発表する。親戚の死に触発されて書き上げられた作品で、古代ギリシャ文学、エドガー・アラン・ポーの作品のモチーフとして用いられている「忘却の薬」に題材をとった神秘的な作風です。また、この作品には、アイスランドの室内楽グループAmiinaが参加し、十代の少女の合唱団の演奏、合唱に脚光が当てられている。
2016年には、ボーカル芸術としてのアンビエントの新たな領域へ踏みだし、サード・アルバム「Will」をDead Oceansから発表する。教会内の広々とした空間性を思わせる独特なヴォーカル形式を確立。このアルバムに収録されている「Nebula」は、アメリカのラジオネットワークNPRにて初演された。この作品を手掛けたデリック・ベルチャム監督のMVは「フィリップ・ジョンソン・グラス・ハウス」にて撮影がおこなわれています。
2019年12月、ジュリアナ・バーウィックはEP「Circumstances Synthesis」をリリース。その後、2020年7月には、これまでの最新作「Healing Is A Miracle」を発表しています。
Julianna Barwickの主要作品
1.「The Magic Place」 Athmatic Kitty 2011
ジュリアナ・バーウィックは、2010年の半ば、最初のアルバムの制作を開始し、翌年のはじめ、この作品を「Athmatic Kitty」からリリースし、ミュージシャンとしての出発を果たす。
一般的に、デビュー作「The Magic Place」は、アンビエント、ニューエイジからの影響が色濃い作品と評されており、バーウィックは前作「Sanguine」よりアンビエントに対する強い接近を試みています。ヴォーカルの形式は実験的です。それはポップスの歌謡曲のようでもあり、教会音楽のようでもある。
先述したように、ジュリアナ・バーウィックは、ヴォーカルのループを多用し、独創的な音響空間をスタジオレコーディングにおいて生み出しています。また、このスタジオ・アルバム全体に、自然味あふれる叙情性、子供のような遊び心が感じられる点について、ジュリアナ・バーウィックは以下のように話しています。
「マジックプレイスは私達の農場の木でした。それは家の後ろの牧草地にあり、上下左右に成長した一本の木でした。それは私達が這う必要があって、そして、その木の中に入ってみると、そこがまた別の空間に続いているような感覚でした。そして私達はその木の枝に横たわることも出来ました。
この作品を「マジックプレイス」と名付けたのは、特に、子供にとって、あの木が魔法のようなものだったからです。それが、今の私の人生についての率直な気持ちです」
ジュリアナ・バーウィックが話しているように、この作品は、彼女のデビュー作としての重要な意味を持つだけでなく、人生の分岐点、神秘的な空間へ繋がる瞬間でもあったのかもしれません。誰にでも以上のような経験はあるはず、子供のときふと見た情景が年をとっても目にやきついているかのような・・・。子供ながらに見たのどかで神秘的な農場の風景、それがのちにバーウィックの重要な音楽性、強固な概念を形作り、ここに新鮮な雰囲気を持つ音楽として再現されています。この後の、ヴォーカルアンビエントの出発点ともなった作品です。
・Apple Music Link
2.「FRKWYS Vol.6:Juliana Barwick Ikue Mori」 RVNG INTL 2011
「FRKWYS Vol.6」は、NYのアンダーグランドシーンで活躍する森郁恵とジュリアナ・バーウィックが共同制作を行った作品で、これまでのバーウィックの作品の中でも最も実験音楽の色合いが強いアルバムです。
しかし、実験音楽だからといって方向性は変わらず、二人の女性アーティストの歌声が生み出す独特な音響性をときにテクノ的な側面、また、実験音楽の側面と、様々な方向からアプローチを図った作品です。聞きやすい作品とはいいがたいものの、ヴォーカルの響きという概念に焦点を絞り、それを美麗なハーモニクスへと昇華している。人の歌声の美しさを追求する二人の日本とアメリカのアーティストの音楽にたいする価値観が見事に合致した興味深い作品です。
・Apple Music Link

Julianna Barwick & イクエ・モリ
価格: 1,528円
posted with sticky on 2022.2.19
3.「Nepenthe」 Dead Ocean 2013
ジュリアナ・バーウィックがデッド・オーシャンとの契約にサインして発表された二作目のスタジオ・アルバム。
一作目よりアンビエント色が強まり、ボーカルトラックの作り込みもさらに洗練されています。「The Magic Place」がバーウィックにとっての幼少時代の農場の懐かしい記憶に立ち返ったものであるとするなら、この作品「ネペンテ」では、さらにそこにルイジアナの教会で聖歌隊に参加していた時代のバーウィックの音楽的なルーツを追求しなおした作品といえるかもしれません。
「ネペンテ」では、ボーカルに、ディレイ、リバーブのエフェクトをほどこし、ミニマル音楽としての要素が一作目より色濃く反映されています。さらに、シンセサイザーのシークエンスを巧みに駆使することにより、教会音楽と、電子音楽の中間にある独創性の高い音楽へと昇華されています。作品で展開される清涼感のあるボーカル、そして、そのボーカルのループエフェクトをミニマル・ミュージックの視点で捉えた、教会音楽のような崇高さを併せもつ。
・Apple Music Link
4.「Will」Dead Ocean 2016
中世ヨーロッパの教会音楽に近い雰囲気を持つアンビエント、前作「ネペンテ」で掲げた音楽性をより先鋭的に突き詰めた作品が、ジュリアナ・バーウィックの通算三作目となる「Will」です。
この作品で、バーウィックはアンビエントの重要な要素のひとつである癒やしという感覚に重きを置き、いくつかの手法、ボーカル、そしてピアノ、さらにはシンセサイザーというこれまでのキャリアにおいて積み上げてきた技術を用い、創造性に富んだ作風を生み出しています。ボーカリストとしての力量もさらに磨きがかかり、本格派オペラ歌手に比する歌声を込めた楽曲もいくつか収録されています。それに加えて、このアーティストの最も重要な気質、癒やしや清涼感といったアンビエンスが随所に漂い、それは、空気の住んだ高原の夜空に浮かぶ星空のような美麗さを想起させます。
・Apple Music Link
5.「Healing Is A Miracle」 Ninja Tune 2020
ジュリアナ・バーウィックを中心に、ヨンシー、メアリー・ラティモア、ノッサジ・シング、といった豪華なヴォーカリストを迎えて制作された通算四作目のオリジナル・アルバム。デッド・オーシャンからNinja Tuneへ移籍しての第一作となります。
これまでの中で最高傑作の呼び声の高い作品です。アルバムのタイトル「Healing Is A Miracle」はジュリアナ・バーウィックが人間の身体の組織の修復について考えを巡らせ、「例えば、手を切ってしまったとき、傷は痛々しくとも、二週間後には見た目の上では、何もなかったようになってしまう、これってなんだかすごいことでしょう」と、我々が見過ごしてしまうような出来事に神秘性を見出したことに因んでいます。
バーウィックは、この作品においてさらに、「自分の力で何かを作り、ただ、愛という形にする・・・・・・それは感動的な体験でした。私がレコーディングしていたのは、自分の心から出てきた音楽であって、決して課題や仕事のためではなかったのだから・・・・・・少しだけ涙することもあった」と語っている通り、純粋な感情を交えて制作された作品で、このアルバムには、純粋なアーティストとしての美しい感情の貫流を感じ取っていただけるでしょう。
・Apple Music Link

















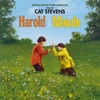



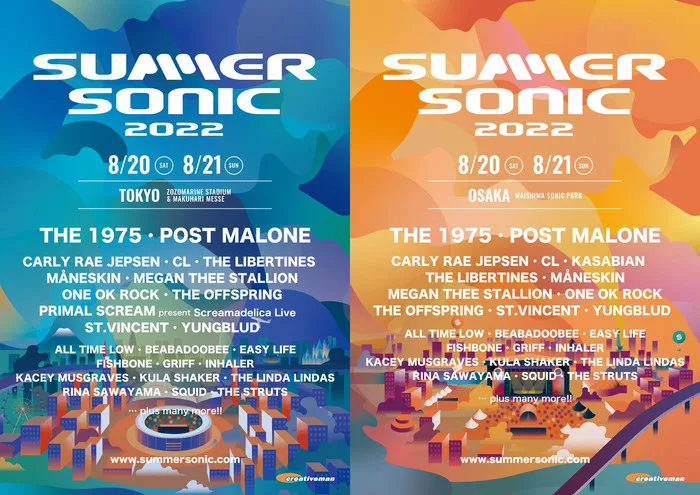





.jpg)













