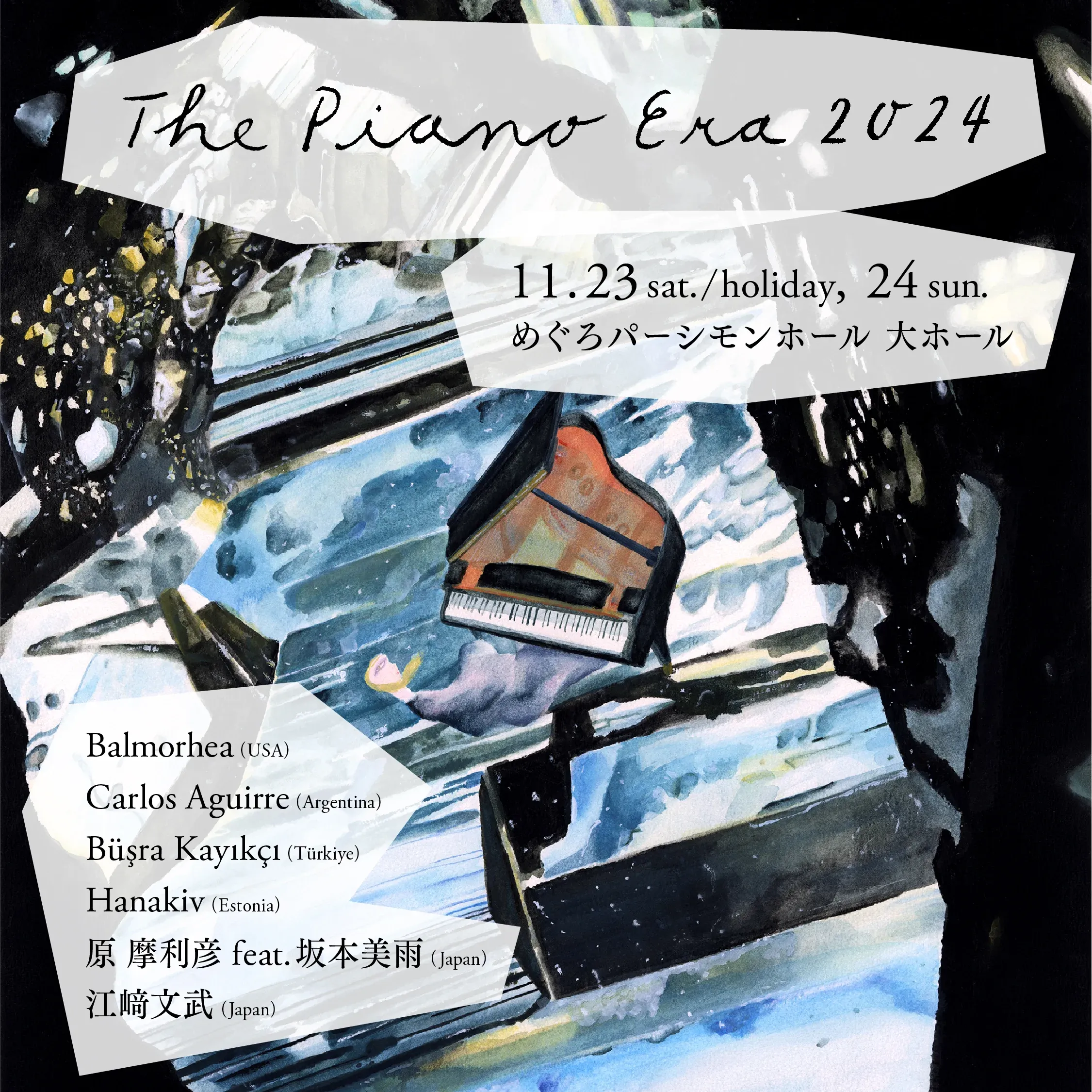そもそも、最初にポスト・クラシカル(Post Classical)という用語を誰が最初に使うようになったかは定かではありません。
しかし、1990年代や2000年代にロックの未来形を意味するポスト・ロック(Post-Rock)という用語が出てきたことと何らかの関連性があるように推察されます。それ以前はアナログ録音が主流でしたが、デジタル・レコーディングが主流となるにつれ、一般的な録音環境にも、デジタル録音の技術が取り入れられるようになっていきました。この流れに乗じて、Protoolsのようなプロ向けの録音ソフトの普及と合わせて、1998年のBill GatesのWindowsの普及、及び、Steve JobbsがもたらしたApple(Mac)の旋風は、個人的な録音の技術に革新性をもたらさずにはいられなかったのです。
特に、今も多くのミュージシャンに愛されているGaregebandがMacの標準的なアプリとして導入されていたことも、専属のエンジニアに使用が限られていたデジタル・レコーディングを一般的に普及させる要因となりました。シンセ音源を別途に購入せずに、ラップトップのキーボードで音源を内臓のスピーカーから出力させるというのは画期的であり、ほとんど発明に近かった。また、この技術はApple Musicのようなストリーミング・サービスの浸透とともに、一般的なアマチュア音楽家にも、デジタル・レコーディングとDTMを普及させていくことになりました。
実は、商業音楽の歴史を概観すると、人工録音と生録音の融合は、その前の時代に、一部の感覚の鋭い音楽家により取り入れられていました。これらは、音楽産業の主要な土地で、ほとんど同時的に発生した動向です。
例えば、90年代には、米国のトータス(Tortoise)がジャズ・ロックとエレクトロニクスを融合させていたし、また、英国のRadioheadは、「OK Computer」の後の時代を通じ、ロックとエレクトロニクスを融合させて、いかにして未知の音楽を生み出すのかを主眼に置いていました。その他、スコットランドのMogwaiは、以前のアイルランドのMBVのエレクトロ・サウンドに触発を受け、デジタル録音と打ち込み音源を巧みに音楽の中に取り入れ、レイヴとハード・ロックをかけ合わせ、ポスト・ロックというジャンルを一般的に普及させる役割を担いました。
そして、このデジタルの録音技術は、さらに全く別のジャンルを生み出すことにも繋がった。 それが今回、名盤特集として取り上げるポスト・クラシカル/モダン・クラシカルというジャンルの正体です。従来まで、クラシカルは一般的に音楽大学や専門の教師から体系的にコンポジションを学び、そして、正当な教育を受けた作曲家のみが楽譜を書き、それらの作品をオーケストラに委嘱し、初演という形でコンサート・ホールでお披露目するというのが常道でした。これは、バッハやモーツァルトが教会側に委嘱され、教会のための音楽を作曲することが多かった中世の時代から、20世紀のイゴール・ストラヴィンスキー、及び、その後のモートン・フェルドマン、フィリップ・グラスの時代までのクラシカルの揺るがぬ伝統性でもあったのです。
確かなことは言えませんが、21世紀の現代音楽の世界でも、基本的にはクラシックという観点から考えてみると、差異はないように思えます。それはスコアとしての記譜が行われた後、オーケストラが初演し、コンサート・ホールの観客がその音楽に裁定を下す、という一連の形が古典音楽としての基本的な作法でした。その合間で、ロベルト・シューマンやロマン・ロランのような音楽評論家たちが、その音楽の良し悪しを詩的かつ文学的に論ずるという過程はありました。
ところが、映画音楽/劇伴音楽のコンポジションをみても分かる通り、現代の古典音楽に触発されたポスト・クラシカルは、体系的な音楽教育を受けたか否かに関わらず、手軽に作曲できるようになっています。
制作のハードルがグッと下がり、オーケストラの楽団を雇わないでも、ソフトウェア音源でオーケストラの代用ができる時代に突入しています。20世紀までは、高名な作曲家が映画のスコアと手掛けるものと相場が決まっていました。そして、その作曲家は、コンポジョションはもとより、オーケストラの記譜法に精通していなければならない決まりになっていた。これは『ゴジラ』のテーマ曲や、古いバージョンの地震速報の環境音を制作した作曲家の伊福部昭を見るとよく分かります。
やがて、20世紀後半になると、著名なポピュラー音楽のコンポーザー/アレンジャー、そして、一般的なミュージシャンでさえも、オリジナル・スコアを普通に手掛けるようになっていき、体系的な音楽教育を受けたコンポーザーと、そうでないコンポーザーの間の差異は、ほとんどなくなっていきました。これは、Stylusのようなオーケストラ楽譜のソフトウェアの普及も大きな効果があったでしょうし、さらに、Logic Studioをはじめとする作曲ソフトウェア、IK Multimedia、East Westなど無数のソフトウェア音源の普及も、同じように映画音楽制作に一役買ったものと推測されます。
つまり、現在の映画音楽の世界では、必ずしもオーケストラ楽団を雇わずとも、ストリングスやホーン、オーケストラ・ヒット、クワイア・コーラスに至るマテリアルを、映画音楽/劇伴音楽の作曲法に取り入れることが可能になりました。この革新性がオリジナル・スコアの制作時に、体系的なオーケストラの記譜法の教育を受けているか否か、という垣根を取り払うことに繋ったのです。
・ポスト・クラシカルの特性 ーその出発点 ヨハン・ヨハンソンの亡き後ー
これまで、私が現代の音楽シーンを語る際、北欧のアイスランドを最重要視して来たのには大きな理由があり、つまり、現代の音楽のジャンルのひとつの出発点はアイスランドにあるかもしれないということです。
結局のところ、映画音楽という観点から、これらのポピュラー音楽とクラシック音楽を融合させて、それらを説得力のある新しいプロダクションとして提出したのが、アイスランドのヨハン・ヨハンソンでした。
彼は、映画音楽という側面で、大きな革新性をもたらしました。生前を通じて、映画音楽に多大な貢献を果たし、その後の時代のポスト・クラシカルの素地を、90年代を通じて形成したと見て間違いありません。
その後、時代を経て、最初にポスト・クラシカル・サウンドの原型を形成したのがベルリンの音楽家、ニルス・フラームです。
彼は、エレクトロニックのプロディーサーとしても傑出しています。ポスト・クラシカルの原型となるドイツのロマン派に触発されたピアノ曲を生み出した。同年代にエレクトロニックのプロデューサーがクラシカル風の音楽を制作するケースはあったと思われますが、フラームはそれをロマン派に触発された作風として、「Wintermusik EP」(2009)という作品を通じて確立しています。
ニルス・フラームはシューベルトのピアノ・ソナタや、ショパンのピアノの小品集のように、ロマンティックで叙情的な東欧圏のピアノ曲の伝統性を現代に復刻しました。そして、エレクトロとオーケストラとの融合は、ニルス・フラームのBBC Promsの公演で世界的に知られることに。同年代、北欧のアイスランドにも、オラファー・アーノルズ(Olafur Arnolds)という傑出した作曲家も誕生しました。両者は後に、実際にコラボレーターとして、共作アルバムを発表することになりました。
これらのポスト・クラシカルの範疇に属する音楽家のピアノの録音には、古典的な気風を反映しながらも、それとは別の録音プロセスが存在していました。それはエレクトロニックやアンビエントといったジャンルの音響性を反映させ、プロダクションに取り入れようという考えなのです。
一例では、ピアノのハンマーをリバーブ/ディレイによって強調させ、ハンマーの音を録音中にノイズ的に処理して取り入れるという趣旨です。 これは後の2010年代になると、数多くの音楽家によって取り入れられ、ミックス/マスタリングとして顕著になっていった傾向です。時にはオラファー・アーノルズのように、特注のピアノを取り寄せ、ピアノの蓋を取り、ハンマーの音をコンデンサー・マイクロフォンで拾い、プロダクションの中に取り入れる手法が確立された。
また、もうひとつ主なポストクラシカルの音楽的な特徴としましては、現代作曲家のグラス、ライヒのミニマルの影響、及び、ドビュッシーやサティの系譜に属する簡素な鍵盤楽器の演奏法があります。
つまり、ミニマル・ミュージックであれば、卓越した演奏力を必要としないため、作曲家としてピアノの演奏に精通していなくとも、良質な作品が生み出すためのハードルが下がりました。かつてのリストやショパンのように、軽やかにトリルやグリッサンドが弾けなくても、また、バッハの「Goldberg Variations」のウィーンの原典版のように装飾音を巧みに弾けなくても、2023年現在では古典派風の音楽を制作することはそれほど困難なことではなくなったのです。
2010年代になると、アイスランドはポスト・クラシカルというジャンルを地元のレイキャビク交響楽団との協力やキャンペーンを通じて、一大的なプロジェクトへと変化させていきました。
その後、複数の優秀なミュージシャンが登場しています。元はニューヨークでファッション・モデルをしていたアイディス・アイヴェンセン(Eydis Evensen)も2020年代のポスト・クラシカルの注目アーティストに挙げられます。また、ポスト・クラシカル、ポップス、ソウルを融合させたAsgeir(アウスゲイル)も登場しました。また、この国の象徴的な歌手であるビョークがポップスの中にオーケストラの対位法を取り入れ、エクスペリメンタル・ポップとして昇華した『Fossora』(2022)を発表したのも、これらのアイスランドの音楽シーンの動向を敏感に察知したからなのです。
・ポスト・クラシカルの波及 ー米国、英国、ヨーロッパ、アジアー
 |
| Keith Kenniff 米国のポスト・クラシカルの先駆者のひとり |
アイスランドに始まり、そしてドイツへと単発的に波及したポスト・クラシカルの動きは、他の音楽産業の盛んな土地へも波及していきます。
そしてその始めこそ、体系的な音楽教育を受けなかった作曲家を中心にもたらされたウェイヴは、逆説的に体系的に音楽教育を受けた音楽家をも取り込み、世界的なムーヴメントへと移行していきました。
特に、この動きを受けて、米国でも複数のミュージシャンがこれらのピアノを中心とする作風に取り組むようになります。
例えば、後に坂本龍一とコラボレーションを行ったキース・ケニフのHeliosとは別のプロジェクト、Goldmundをはじめ、古典的なロマン派の音楽に触発されたピーター・ブロデリックなど、才気煥発なポスト・クラシカルに属する音楽家が、2010年代を通じて活躍するようになった。また、イギリスでも、この動きと関連する音楽家が出現し、マンチェスターのDanny Norburyというチェロ奏者もシーンの一角を担う存在でしょう。
さらに、フランス、オランダからも個性的なポスト・クラシカルアーティストが登場した。さらに、アジアにもこの音楽に触発を受けた音楽家が数多く登場しています。
エレクトロニカの傑作『Sail』を2003年にリリースし、映画音楽やドラマ音楽等で活躍する高木正勝は、同じピアノの録音技術を取り入れて、日記のような形で、bandcampでポスト・クラシカルの作品「Marginalia」を発表しつづけています。現時点では140のシングルが発表されています。
また、先日、イギリスのクラシックの名門、Deccaと契約を交わし、最新作を発表した小瀬村晶も2010年代から率先してこのジャンルに取り組んできた象徴的な音楽家です。
また、日本を離れて、ロンドンの音楽シーンで注目を浴びるシンセ奏者/歌手の大森日向子もポスト・クラシカルに触発された曲を発表しています。同じく、ロンドンの実験音楽/エクスペリメンタル・ポップのシーンで活躍し、イタリアの教会等でライブを行うHatis Noitもモダン・クラシカル系のアーティストとして活躍の裾野を広げ始めています。どこからどんなアーティストが出てくるのか、まったく予測がつかないというのが、このジャンルの最も面白い点でしょう。
上記のことは、すでに過去のアーカイブで何度も部分的に言及してきましたが、今回、改めて体系的にまとめておくことにしました。ひとつ補足しておくと、ポスト・クラシカルというジャンルは、必ずしも単一の音楽として存在するわけではありません。ときには、エレクトロニック・プロデューサーがキャリアの一作品において、あるいはアルバムの中に小休止のような形として、ポスト・クラシカルに属する作品をリリースしたり、収録したりする場合もあります。
例えば、全般的に見ると、FenneszとSakamotoの共作『Cendre』はテクノでもあり、アンビエントでもあり、ポスト・クラシカルであるということになるでしょう。もちろん、見方によれば、Clarkの『Playground In A Lake』もオーケストラがあるので、ポスト・クラシカルに属すると見ても違和感はありません。インディーフォーク/アンビエントの音楽家で、建築のアートやファッション・デザインの領域でも活躍するGrouperの『Ruins』もポスト・クラシカルに属するということになるでしょう。
つまり、ポスト・クラシカルは、少なからず他のジャンルに溶け込むようにして存在する音楽というのが妥当な見方となるはずです。また、もちろん、それとは反対に、ポスト・クラシカルの音楽が別の音楽と結びつく場合もあります。これは一般的には指摘されていませんが、ラナ・デル・レイの新作『Did You Know〜』にも、クラシカルとポップスの合致を見出すことができるでしょう。
下記に掲載するディスク・ガイドもいつもと同じように駆け足となってしまいますが、このジャンルの代表的な作品をピアノ曲を中心にご紹介していきます。入門的なガイドとしてご活用下さい。
・ポスト・クラシカル/モダン・クラシカルの名盤
Hans Otte/Herbert Henck-『Das Bach Der Klange』(1999 ECM)
ドイツのシュヴァルムシュタットのヘルベルト・ヘンク(Herbert Henck)はミニマリズムを得意とするピアニストである。
これまで、ジョン・ケージ、チャールズ・アイヴズ等の演奏作品を残している。ECMより発売されたアルバムにおいて、ヘルベルト・ヘンクは同国の現代作曲家、ハンス・オットに脚光を当てようとしている。ハンス・オット(Hans Otte)は、パウル・ヒンデミットに作曲を学び、指揮をヘルマン・アーベントロート、ピアノをブロニスラフ・フォン・ポズニャックに師事している。
ヘルベルト・ヘンクはこの作品について、「この録音は、ある意味で、現代ピアノ音楽の中で最も注目に値する作品のひとつであり、書かれてから20年が経過しても、その美しさ、純粋さ、力強さは少しも失われていないと信じています」 と説明している。
ライヒ、グラス、ライリーの系譜にあるミニマリズムに属するピアノ作品集。倍音を活かした演奏法は凛とし、気高い精神性すら漂う。反復の演奏を通してモダン・ピアノの音響性の極致を追求した画期的な作品の一つ。
Sylvain Chauveau- 『Un Autre Decembre』(2003 FatCat)
フランスのバイヨンヌ出身のシルヴァン・シャヴォー(Sylvain Chauveau)は、最も早い時代に、ピアノ演奏家としてポスト・クラシカルの作品に挑戦した音楽家の一人。クラシカルの作風に加え、電子音楽の作品も発表している。
シルヴァン・シャヴォーは、現在は分からないが、当時、楽譜の読み書きができず、自分が何の音を弾いているのかさえわからないまま、この秀逸なクラシカル風のアルバムを制作している。
ピアノ、弦楽器、木管楽器のための ピアノ、弦楽器、木管楽器のための美しくエレガントでミニマルな小品は、重層化され、電子音響のグリッチで処理されている。20世紀初頭の室内楽、ミュージック・コンクリート、ニューウェーブ映画からインスピレーションを得たという彼の作品は、まさにモダン・フレンチと称すべき。シンプルな演奏で、淡々としているが、そこには近代ヨーロッパの叙情的なピアノ曲の気風も漂う。ポスト・クラシカルを語る上では不可欠な作風の一つ。
Nils Frahm 『The Bells』 (2010 Erased Tapes) /「Wintermusik」EP(2009 Erased Tapes)
後には、電子音楽/エレクトロニックの傑作を多数残しているベルリンの演奏家/作曲家、ニルス・フラームは、現在もイギリスを中心に人気を獲得している。後に発表するエレクトロニックとミニマリズムを融合させた作風が主要な作風であるが、最初期はポスト・クラシカル風の作風を残していた。
2021年には初期のポスト・クラシカルの未発表曲を中心に収録した『Old Friends New Friends』も発表している。
現時点から見ると、御本人は、この時代の作風について、「ドイツ・ロマン派的」であるとしており、古びた作風であると捉えているらしい。最初期に発表した三曲収録の「Wintermusik」、それに続いて発表された『The Bells』は、ポスト・クラシカルをより有名にする役割を担った作品である。
「Wintermusik」では、ドイツ・ロマン派に属する叙情的なピアノ曲を制作している。ミニマリズムに根ざした音楽性ではありながら、後に2010年代にかけて電子音楽という領域で開花する曲の想像力や構成力という面で非常に光るものがあり、相対音感や和音のセンスという面では現在の音楽家でも傑出している。
翌年に発表された『The Bells』は、ベートーヴェンのピアノ・ソナタに比する荘厳さと厳粛さを兼ね備えたゲルマン魂に溢れた硬派なピアノ作品集。以前から追求してきたポスト・クラシカルの作品は、本作においてひとまず集大成を迎えた。制作者本人がどう思っているのかまではつかないが、後の複雑な構造性を擁する電子音楽の原点は、2010年前後の作風に求められると思われる。
Olafur Arnolds 『Some Kind of Piece』ーPiano Reworks (2022 Universal Music)
アイスランドを代表する作曲家で多数のコラボレーターとの共作を残し、そして、グラミー賞ノミネートのプロデューサーとしても知られ、地元のレイキャビク交響楽団との共演を果たしているオラファー・アーノルズ。まさに現代のアイスランドの顔とも言っても差し支えないだろう。また、アーノルズはソロ名義にとどまらず、Kiasmosとして活動し、秀逸なエレクトロニックを制作し、現在、自主レーベルも立ち上げ、多岐にわたる分野で活躍している。
最初期はエレクトロニックを中心に制作していたプロデューサーではありながら、映画音楽やピアノを中心にソングライティングを行うにつれ、ポスト・クラシカル・シーンの先鋒として強烈な存在感を持つに至った。上記のニルス・フラームとは音楽的盟友であり、共作アルバムも発表している。
そして、ピアノ作の最高傑作は、パンデミック時代に発表された「Some Kind of Piece」、さらに続いて発表されたリワーク『Some Kind of Piece』ーPiano Reworksとなるだろう。知人の音楽家を中心にアーノルズの作品の再構成に挑戦している。
この作品について、アーノルズは、「作品は提出してそれで終わりというわけではない」と語る。本作の録音には、Eydis Evensen、Hania Rani,JFDR、イルマなど、国境や地域を越え、複数の音楽家が参加。韓国のイルマの「We Contain Multitudes」は、原曲よりテンポがゆっくりとなっている。この曲は「From Home」バージョンのシングルとしても発売されている。
Peter Broderick 『Grunewald』EP (2016 Erased Tapes)
オレゴン州カールトン出身の作曲家、ピーター・ブロデリック(Peter Broderick)はソロ名義の活動のほか、Efterklangのメンバーしてセッション・ミュージシャンとしても活躍している。叙情的でスタイリッシュな音楽を制作するプロデューサーであり、ポスト・クラシカルからエレクトロニック、ボーカル・トラック入りのオルト・フォークに至るまで、ジャンルに規定されない幅広い音楽を制作している。哲学者のような風采も実際の音楽性に説得力を与えていることは疑いがない。
2023年にはピアノ曲を中心としたフル・アルバム『Burren』を発表している。これまで複数のシングルを含め、断片的にポスト・クラシカルという領域にある表現性を拡張してきた。制作者の音楽性の原点となった作品群が、2010年のフルアルバム『How They Are』、2016年に発表されたEP『Grunewald』、2020年に発表されたシングル「Ernest Layers」である。
本作は、その後のErased Tapesの録音上のコンセプトに強い影響を及ぼした作品であろうと思われる。教会建築のような特殊な音響性やアンビエンスを活かしたピアノ曲は静謐な印象があり、そして安らぎに充ちている。
ストリーミングでも多くの再生数を記録しており、本作のクローズとして収録されている「Eyes Closed and Traveling」は、モダンなピアノ曲としては最高峰に位置する名曲の一つ。この曲は、シングル・カット・バージョンとしても発売されていて、ファンタジックな着想が込められながらも、深い叙情性を漂わせている。
古典的なヨーロッパのピアノ曲の気風を受け継ぎながらも、その着想の中には音の配置や空間性からもたらされる建築学的な美学が潜んでいる。ミニマリズム、モダニズム、ポスト・モダニズムという芸術的な概念が複合した結果、これまでありそうでなかったスタイリッシュなピアノ曲が生み落とされることになった。
amiina 『YULE』 (Aamiinauik Ehf 2022)
アイスランドの室内楽グループ、amiinaはエレクトロニカと弦楽四重奏をかけあわせた音楽性が魅力。テルミンやクレスタ等の音色を駆使し、おとぎ話や絵本のような可愛らしい世界を音楽により構築している。エレクトロニカ色の強い室内楽としては、『Kurr』、『The Lightning Project』等の良作を発表している。
ミニ・アルバム『YULE』は2022年のクリスマス直前に発表された、グループのクリスマスのための室内楽の曲集となる。近年、エレクトロニカと弦楽器の融合にメインテーマを置いていたアミーナ。
12月9日に自主レーベルから発売されたミニ・アルバムでは、電子音楽の要素を排し、チェロ、ビオラ、バイオリンをはじめとする室内楽の美しい響きを探究している。このリリースに際して、amiinaは、「クリスマスの楽しみのために、これらの細やかな室内楽を提供する」とコメントを出しているが、その言葉に違わず、クリスマスで家庭内で歌われる賛美歌に主題をとった聞きやすい弦楽の多重奏がこのEPで提示されている。
アルバムの全7曲は細やかな弦楽重奏の小品集と称するべきもの。厳格な楽譜/オーケストラ譜を書いてそれを演奏するというよりも、弦楽を楽しみとする演奏者が1つの空間に集い、心地よい調和を探るという意味合いがぴったりで、それほど和音や対旋律として、難しい技法が使われているわけではないと思われるが、長く室内楽を一緒に演奏してきたamiinaのメンバー、そして、コラボレーターは、息の取れた心温まるような弦楽器のパッセージにより美麗な調和を生み出している。賛美歌のように調和を重んじ、amiinaのメンバーは表現豊かな弦のパッセージの運びを介し、独立した声部の融合を試みている。
これらの楽曲はほとんど3分にも満たない小曲ではあるけれど、クリスマスの穏やかで心温まるような雰囲気を見事に演出している。
Danny Norbury 『Light In August』(2014 flau)
マンチェスターのチェロ奏者、ダニー・ノーベリー(Danny Norbury)は、ソロ活動にとどまらず、ナンシー・エリザベス、ラファエル・アントン・イリサーリ、ライブラリー・テープスの作品やライヴなどで名脇役として活躍する。
多作な演奏家ではないが、これまでのソロ名義で発表された三作のアルバムは、いずれも濃密な音楽的な主題に下支えされている。
ダニー・ノーベリーの音楽の主題は、本式のアコースティックなチェロ演奏に加え、ラップトップを介して出力されるエレクトロニクスの融合である。ライブのステージでは実際の彼の演奏に加え、ラップトップをステージに持ち込み、2つの視点による音楽が融合を果たす場合もある。
特に、ウィリアム・フォークナーに触発された2014年のアルバム『Light In August』は、ピアノとチェロとエレクトロニクスが劇的な融合を果たしたポスト・クラシカルの傑作である。
決してテクニカルではないが、ピアノの演奏の瞑想性、思索性、その内側に漂う静謐さ、それらの空間性の中をノーベリーの重厚なチェロの演奏が幽玄に舞う。ときに、ノーベリーのチェロはノイズや不協和音という形をとって抽象的な空間に立ち表れ、調和的なピアノの演奏になごやかに溶け込んでいく。潤沢な午後のひとときを約束する、穏やかさに充ちた時間の連続。
Goldmund 『Sometimes』(2015 Western Vinyle)
キース・ケニフは米国の音楽家で、現在、妻のホリー・ケニフがドリーム・ポップ/アンビエントのプロデューサー/ギタリストとして頭角を表しつつある。現在もピアノを通じて良作を発表し続けている。
元々は、エレクトロニック・プロデューサー名義のHeliosとして活動していたキース・ケニフではあるが、ヘルマン・ヘッセに触発されたと思われるGoldmund名義では、良質で聞きやすいピアノ作品、そして現代的なテクノロジーとアメリカーナをシームレスにクロスオーバーしたインディーフォークを制作している。とりわけ、ピアノ作品としては、『The Malady Of Elegance』、そして『Sometimes』が代表作として挙げられる。前者は、色彩的な和音性を突き出したアイディアに富む。後者は、それらの作風にゴシック調のストーリー性を加味した内容となっている。
また、この作品には、坂本龍一が『A Word I Give』でコラボレーターとして参加している。この時代、かれは、Alva Notoとのグリッチ・ユニットはもちろんのこと、キース・ケニフや、アンビエント・シーンで活躍目覚ましいジュリアナ・バーウィックともコラボレーションを図っていた。当時、坂本龍一は、彼より若い音楽家との共同制作に積極的な姿勢を示しており、「若い音楽家から提案があれば、いつでもコラボレーションしたい」と話していた時代が今ふと思い出される。
Akira Kosemura 『In The Dark Woods』 (2017 1631 Recording AB)
小瀬村晶は、英国のデッカと契約し『Seasons』という傑作を発表しているので、国内のミュージシャンとは言いがたくなりつつある。もちろん、他分野で活躍なさっている音楽家である。ピアノ曲を書き、あるときは映像のための音楽を作り、もちろんレーベルオーナーとしての表情を持つ。
これまでLibrary Tapesに近い、ミニマリズムに触発を受けたピアノ曲を2010年代を通じて書いてきたが、一応その継続した活動の集大成と呼ぶべき作品が『In The Dark Woods』となる。
これまで多数のドラマや映画音楽を手掛けていることもあってか、音楽の視覚性(サウンドスケープ)と実際の音の構造を結びつける力量は他を凌駕するものがある。アルバムのアートワークに代表されるように、幽玄な森を彷徨うかのような神秘性が本作の最大の魅力となっている。
実際のピアノの演奏力は巧みであるが、技術を披瀝するわけではなく、クラシックに詳しくないリスナーにもその良さをシンプルに伝えようとしている。ある意味では、長期的な活動を通じて、この作品を一つの区切りとして、現在はより深みのあるピアノ曲に取り組まれているという印象を受ける。
Henning Schmiedt 『Piano Day』(2021 flau )
本稿は、パートナーシップの関係にあるflauを持ち上げようとして作成したわけではなかった・・・。しかし、結局、より良いプレイリストを制作しようとしたら、flauから2つの作品が登場していた。
リスナーとしては、メジャー/インディーを問わず、レコード・レーベルだけで聴くものではないと思うが、好きな音楽を探すためのひとつの指針として、「レーベル」という概念は存在すると言って良いかもしれない。また、Labelという意味は、単なる一企業を示すものではなく、主宰者の考えや人生観が深く反映されている。それは、どちらかといえば、「人生の流儀」とも称するべきものなのだ。ECMもそうだし、ラフ・トレード、もちろん4ADも同じである。また、もっと細かいところでいえば、ディストロ等をやっている個人レコード店も同様だろうか。レーベルに関しては、音楽的な側面のみで一括りにして語り尽くせるものでもないと思っている。
現時点のポスト・クラシカルを中心とするレーベルの最高峰としては、日本/東京のflauか、あるいは、その先駆者である英国/ロンドンのErased Tapesということになるかもしれない。 結局、この2つのレーベルは、ポピュラー寄りのクラシカルに属する作品の普及に関して多大な貢献を果たしてきた経緯がある。また、それはflauがFADER等の海外の大手メディアにも紹介されていることからもわかる。ジャンルレスに良い音楽を広めようというのが、両レーベルの共通項でもあるのかもしれない。
さて、 Henning Schmiedtについて、私は十数年前からその存在こそ知っていたのだったが、特にポスト・クラシカル系のピアノ演奏家として、最高峰にあるのではないか、という考えを持っていた。しばらく時間が経ち、そして、様々な驚愕的な出来事が起こり、またほとんど何も起こりもしない日々もあり、全然別のジャンルを聴いたり、また、音楽そのものから離れていたせいもあって、その存在も長らく忘れかけていた。
旧東ドイツ時代の出身のベテラン作曲家、へニング・シュミートはモダン・クラシックにとどまらず、ワールド・ミュージック、ジャズと複数のジャンルを深く知悉した音楽家だ。最初に挙げたハンス・オットとは別の領域に属する演奏家であるが、十数年前に、ECMのカタログと並んで、このアーティストの音楽を聴いた時の印象としては、リラックス感のあるピアノ曲という感じだった。頭でっかちではない、感性を元にしたピアノ曲として印象に深く残った。そして、今回、あらためて、へニング・シュミートの代表作とも言える『Piano Day』を聴いて分かるのは、当時の最初の印象や直感がまったく間違っていなかったということである。
今聴いても、このアーティストに関して、当初の鮮烈な印象はほとんど揺らぐことはありません。それどころか、その信頼度に関しては従来よりも強まり、当時の印象をはるかに凌ぐものすらある。
ピアノの演奏は凄くシンプルなのにも関わらず、そこには、作曲家のピアノへの愛情が溢れ、音のひとつひとつには煌めきがあり、和らいだ風が通り抜けていくかのような錯覚すらある。ハンス・オットの建築学的な興味に裏打ちされたミニマリズムとは対象的に、一般的に開かれたミニマリズムの最高峰に、へニング・シュミートは到達している。旧来の堅苦しいドイツ・アカデミズムからの音楽概念の開放というのを、制作者は主なテーマに置いているのかもしれない。
子供からお年寄りまで年齢を問わず楽しめる、素晴らしいポスト・クラシカルであり、現時点でこれ以上の作品は存在しない。少なくとも、何歳になってもこういった音楽を好きでありつづけたい。
Hania Rani 『On Giacometti』(Gondwana Recrods 2023)
近年、ポスト・クラシカルの作品を中心に良質なカタログを発表しつづけているマンチェスターのGondwana Recordsは、2020年代を通じて、ロンドンのErased Tapesとともに、この「ポスト・クラシカル」というジャンルを急成長させる大きな役割を担うことだろう。ポーランドのシンセサイザー演奏家/ピアニスト/作曲家のハニャ・ラニは、彫刻芸術を中心に数々の名作を残した同名のスイスのアート界の巨人のための映像作品のサウンドトラックに挑戦した。
ハニャ・ラニ(Hania Rani)は、このピアノを中心とする作曲集を録音するため、友人が所有する山岳地帯の山小屋に冬の期間滞在し、これらのピアノ曲集を書き、その年の春に山小屋を後にした。ヨーロッパの大規模のライブ・イベントではシンセサイザー奏者として知られているミュージシャンであるが、この作品では徹底したピアノによるミニマリズムを展開させ、アルベルト・ジャコメッティの抽象主義/シュールレアリズムをリズミカルなピアノ演奏を通じて表現しようとしている。
フレドリック・ショパンの生誕の地からこのアーティストが出てきたのは偶然ではなく、時代に要請されてのことである。同地の音楽大学で学んだ本式の作曲法や演奏法を元にして、制作者のファッション・センスとアート・センス、そして豊かな感性や叙情性を複合させ、聞きやすく、そして聴き応えのあるポスト・クラシカルのニュー・トレンドが生み出された。ハニャ・ラニは、オラファー・アーノルズの作品にも参加しているが、今後、ヨーロッパ圏を中心に、ポスト・クラシカル・シーンやエレクトロ・シーンで大きな注目を集めることが予想されます。
Gia Margaret 『Romantic Piano』 (2023 Jagujaguwar)
ポップという観点からは過度な注目こそ受けていない印象もあるGia Marharetではあるものの、この作品はミュージシャンの最高傑作と断言したい。jagujaguwarのレーベルの方はこの作品をそれほど強く推してはいない感じであったが、今作は、アメリカではなく、イギリスやヨーロッパ圏で広く受け入れられそうな作風である。
元々、ポピュラー・シンガーとして活躍をしていたシカゴのGia Margaretは、声が一時的に出なくなり、その後にピアノの作曲へとシフト・チェンジしていった。エレクトロニックを交えたクラシカルへと転向した前作のアルバムに続き、「Romantic Piano」はピアノ、ギター、テクノといった、このジャンルの主要な音楽性をシームレスにクロスオーバーしている。虫の声などのアンビエント風のサンプリングが取り入れられているのにも注目したい。
ピアノの楽譜を書いた後、グリッチ/ディレイ等のエレクトロの加工を施し、それらをセンス溢れるポピュラーなクラシック音楽へと昇華させる技術は傑出している。穏やかな日々の幸せを噛み締め、それらをセンス抜群のオシャレかつスタイリッシュなピアノ曲へと昇華させている。
アルバムの中では、オルト・フォークとしても聞ける「Guitar Piece」も秀逸で、モダン・ポップスとして鮮烈な印象を放つ「City Song」も捨てがたい。きわめつけは、Aphex Twinへのオマージュを示したと思われる「April to April」では、ピアノ曲を通じて新たなフェーズへと踏み入れている。
これから、ボーカル曲を制作するのか、それともインスト曲を制作するのかは本人次第であるものの、そのどちらに進むにしても未来は明るいと思う。以後、耳の肥えたリスナーから注目を集めても不思議ではないでしょう。
Nils Frahm 『Day』 (2024 leiter)
今回の最新アルバム『Day』は個人スタジオがあるファンクハウスから距離を置いている。このファンクハウスの個人スタジオは、『All Melody』のアルバムのアートワークにもなっている。なぜ制作拠点を変更したのかについては、東西分裂時代のドイツの閉塞感から逃れることと、作風を変化させることに狙いがあったのではないかと推測される。
フラームは、以前からドイツの新聞社、”De Morgen”の取材で明らかにしている通り、ワーカーホリック的な気質があったことを認めていた。しかし、そのことが本来の音楽的な瞑想性や深遠さを摩耗していることも明らかであった。おそらく、このままでは、音楽的な感性の源泉がどこかで枯渇する可能性もあるかもしれない。そのことを知ってのことか、ニルス・フラームは、2021年頃から、ライブの本数を100本ほどに徐々に減らしていき、パンデミックやロックダウンを契機に、彼のマネージャーと独立レーベル、”Leiter-Verlag”を設立し、その手始めに『Music For Animals』を発表した。これらの動向は、次の作品、そして、その次なる作品へ向けて、以前の活動スタイルから転換を図るための助走のような期間であったものと考えられる。
フラームは、活動初期のコンテンポラリークラシカル/ポスト・クラシカルの未発表音源を収録した2021年の『Old Friends New Friends』では、自身のピアノ曲を主体とする音楽性について、「ドイツ・ロマン派」的なものであるとし、いくらかそれを時代遅れなものとしていた。その後の『Music For Animals』はシンセサイザーによるアンビエント作品であったため、しばらくはピアノ作品を期待出来ないと私は考えていたのだったが、結局のところ、このアルバムで再び最初期の作風に回帰を果たしたことは、ある種のブラフのような言葉だったのだろう。
しかし、原点回帰を果たしたからといえど、過去の時代の成功例にすがりつくようなアルバムではない。はじめに言っておくと、このアルバムはニルス・フラームの最高傑作の1つであり、ピアノ作品としては、グラミー賞を受賞したオーラヴル・アルナルズの『Some Kind Of Piece』に匹敵する。全編が一貫してピアノの録音で占められていて、あらかじめスコアや着想を制作者の頭の中でまとめておき、一気呵成に録音したようなライブ感のある作品となっている。
ここ数年の称賛された作品や、売れ行きが好調な作品を見るかぎりでは、そのほとんどが数ヶ月か、それ以上の期間がアルバムの音楽の背景に流れているのを感じさせるが、『Day』は、ほとんどそういった時間の感慨を覚えさせない。制作者によるライブ録音が始まり、それが35分ほどの簡潔な構成で終了する。多分、無駄な脚色や華美な演出は、このアーティストには不要なのかもしれない。フラームのアルバムは、ピアノの演奏、犬や鳥の鳴き声のサンプリング、そして、マイクの向こう側にかすかに聞こえる緊張感のある息遣いや間、それらが渾然一体となり、モダン・インテリアのようにスタイリッシュに洗練された音楽世界が構築されたのである。