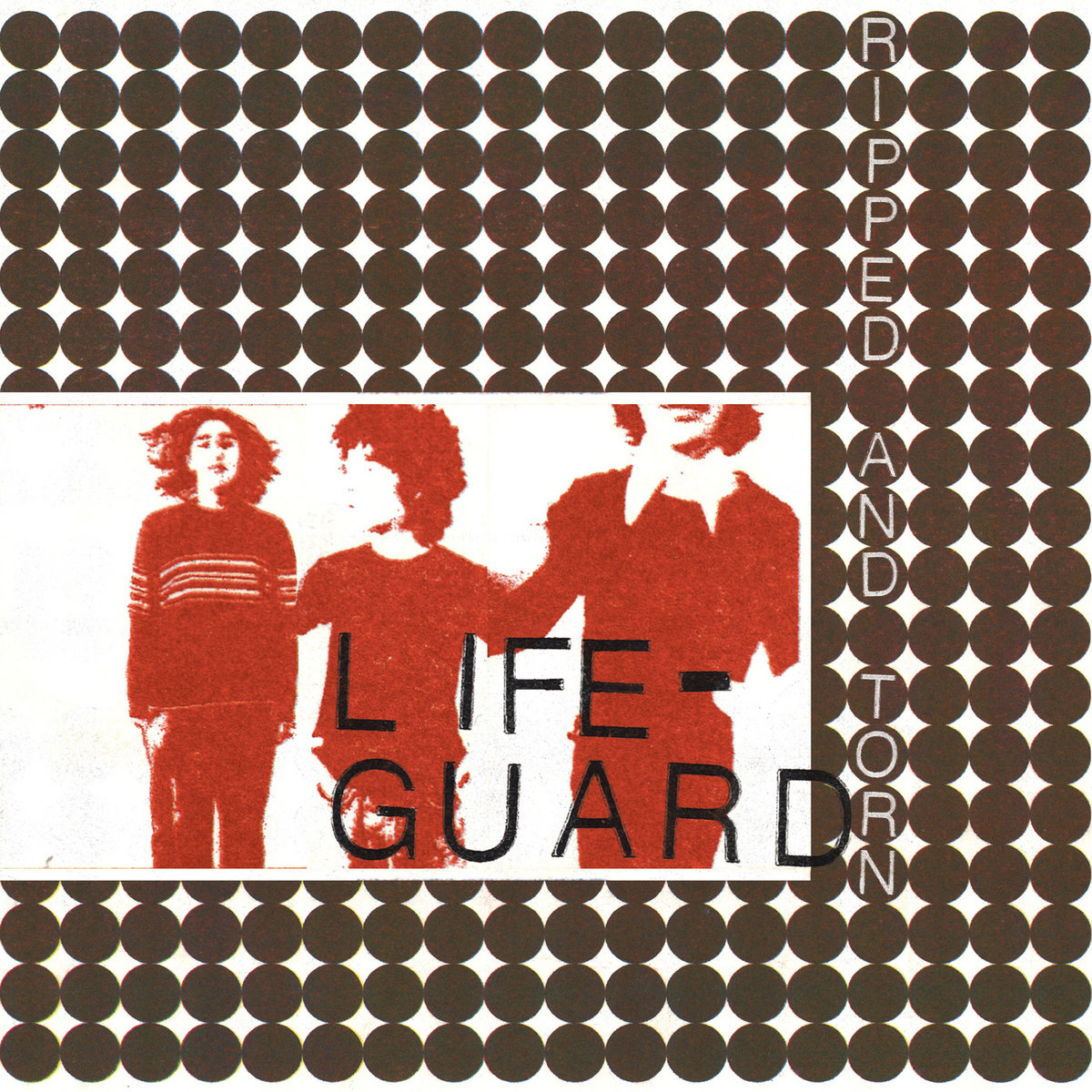今年初め、BC,NR(ブラックカントリー、ニューロード)は3作目のアルバム『Forever Howlong』をアナウンスした。続いて、彼らは最初のリードシングル「Besties」に直接インスパイアされたという「Happy Birthday」を配信した。「『Happy Birthday』を書いた時、頭の中にはジョージアの曲『Besties』があったんだ。だから、この曲の構成はその曲の影響を強く受けているんだ」
この曲は、レスリー=アン・ローズが監督したストップモーションのビデオと同時公開された。発表されたばかりのUKでのライブを含む、バンドの今後のツアー日程とともに、以下でチェックしてほしい。
Black Country, New Road 2025 Tour Dates:
Mon 7 Apr – Plaza – Stockport, UK
Tue 8 Apr – Queens Hall – Edinburgh, UK
Wed 9 Apr – Leeds Project House – Leeds, UK
Fri 11 Apr – Town Hall – Birmingham, UK
Sat 12 Apr – Engine Rooms – Southampton, UK
Sun 13 Apr – Epic Studios – Norwich, UK
Sat 3 May – Pitchfork Music Festival CDMX – Ciudad De México, MX
Tue 13 May – Salt Shed – Chicago, IL, US ☼ ☆
Wed 14 May – Slowdown – Omaha, NE, US ☼
Fri 16 May – Mission Ballroom – Denver, CO, US ♢
Sat 17 May – Kilby Block Party – Salt Lake City, UT, US
Mon 19 May – The Observatory – Santa Ana, CA, US ☆
Tue 20 May – The Wiltern – Los Angeles, CA, US ☆
Thu 22 May – The Warfield – San Francisco, CA, US ☆
Fri 23 May – Roseland Theater – Portland, OR, US ☆
Sat 24 May – Moore Theater – Seattle, WA, US ☆
Fri 23 May – Roseland Theater – Portland, OR, US
Sat 24 May – Moore Theater – Seattle, WA, US
Sat 7 Jun – Primavera Sound Festival – Barcelona, ES
Wed 13-Sat 16 Aug – Paredes de Coura Festival – Porto, PT
Thu 28 Aug – End of the Road 2025 – Dorset, UK
Thu 11 Sep – Rock City – Nottingham, UK
Fri 12 Sep – Albert Hall – Manchester, UK
Sat 13 Sep – Albert Hall – Manchester, UK
Mon 15 Sep – Olympia – Dublin, IE
Tue 16 Sep – Olympia – Dublin, IE
Thu 18 Sep – Barrowlands – Glasgow, UK
Sat 20 Sep – Sage – Gateshead, UK
Mon 22 Sep – Beacon – Bristol, UK
Wed 24 Sep – Corn Exchange – Cambridge, UK
Thu 9 Oct – Casino de Paris – Paris, FR
Fri 10 Oct – Stereolux – Nantes, FR
Sun 12 Oct – Paradiso – Amsterdam, NL
Mon 13 Oct – Paradiso – Amsterdam, NL
Tue 14 Oct – Gloria – Cologne, DE
Wed 15 Oct – Astra – Berlin, DE
Fri 17 Oct – Vega – Copenhagen, DK
Sat 18 Oct – Fallan – Stockholm, SE
Sun 19 Oct – Sentrum Scene – Oslo, NO
Tue 21 Oct – Mojo – Hamburg, DE
Wed 22 Oct – Roxy – Prague, CZ
Thu 23 Oct – Les Docks – Lausanne, CH
Sat 25 Oct – Magazzini Generali – Milan, IT
Sun 26 Oct – Epicerie Moderne – Lyon, FR
Tue 28 Oct – AB – Brussels, BE
Thu 30 Oct – The Dome – Brighton, UK
Fri 31 Oct – O2 Academy Brixton – London, UK
☼ support from Friko
☆ support from Nora Brown with Stephanie Coleman
♢ supporting St. Vincent