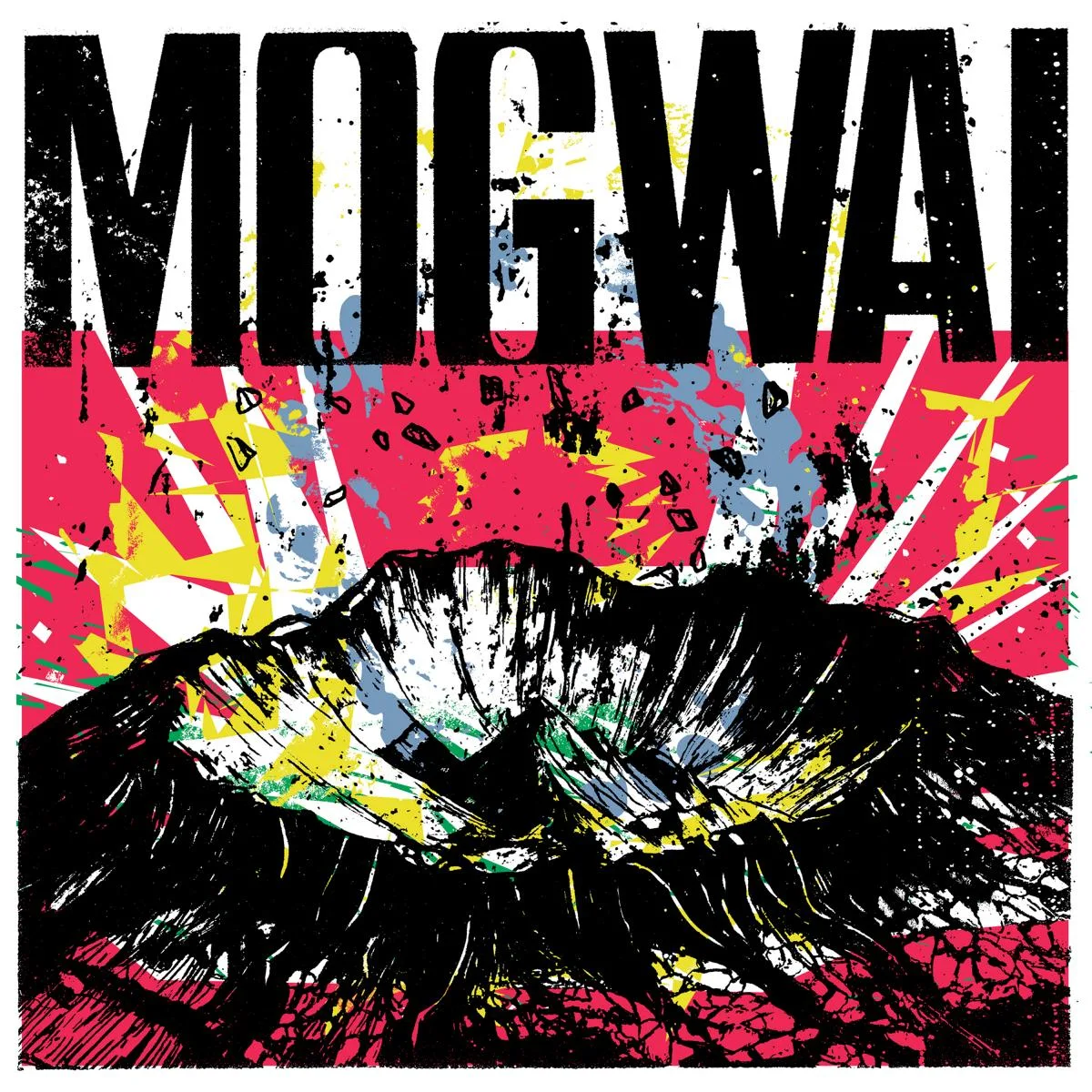|
今週金曜日に、Water From Your Eyesが『It’s a Beautiful Place』をリリースします。このアルバムは、デュオの鮮やかなクローム調の傑作で、ローリング・ストーン誌はこれを「彼らの最も喜びに満ちた、大胆不敵な作品」と称賛しています。
本日、アルバムの明るく広がりのある3rdシングル「Nights in Armor」を聴き、ジョ・シャファー監督によるミュージックビデオをご覧ください。
「Nights In Armorは、当初『Grill』という奇妙なLoreleiの曲として始まりました」とWFYEのNate Amosは説明します。
「リフが曲よりもクールだと感じていたので、新しいトラックに再利用し、ギターパートを根本的に異なる文脈に置くために、他の楽器を追加しました。これにより、ギターがどのような感情的な役割を果たせるか試したのです。「ボーカルのフックを書くのに苦労したのを覚えています。ある部分で逆再生し、逆再生したメロディを中心にベースラインを構築したと思います」
バンドは現在、ステージ上でアル・ナルド(ギター)とベイリー・ウォロウィッツ(ドラムス)を加えた4人編成となり、『It's A Beautiful Place』をプロモーションするため、北米とヨーロッパでの大規模なヘッドラインツアーを実施します。
前者(北米ツアー)は9月22日にフィラデルフィアでスタートし、11月2日のデンバーまで続き、ニューヨークのBowery Ballroom、ロサンゼルスのLodge Room、シカゴのSleeping Villageなどでの公演を含む。後者(ヨーロッパツアー)は11月13日にロンドンのVillage Undergroundで始まり、12月7日にリスボンのMusicboxで終了する。
2023年の『Everyone's Crushed』(マタドール・レコードからのデビュー作で批評家から高い評価を受けた作品)以来、レイチェル・ブラウン(they/them)とネイサン・アモス(he/him)は、都市のオルタナティブ音楽シーンの柱となり、最も尊敬されるアンダーグラウンドバンドとなりました。
彼らはインターポールのツアーでサポートアクトとして巨大なステージで演奏し、メキシコシティで16万人のファンを前にパフォーマンスしました。
地元では、イースト・リバーでDIYボートショーのフランチャイズを設立し、都市の音楽の最前線にある友人たち——YHWH Nailgun、Model/Actriz、Frost Children、Kassie Krut——をホストしてきました。ブラウンは「thanks for coming」名義で新しいEPをリリースし、アモスはソロプロジェクト「This Is Lorelei」で高い評価を受けたフルアルバムをリリースしました。
デュオは昨年夏に『It’s a Beautiful Place』を完成させました。これはWFYEの他のリリース同様、アモスの寝室で、モーク&ミンディ時代の破れたロビン・ウィリアムズのポスターの下で制作されました。「要するに」とアモスは冗談を交えて言う。「ロビンはウォーター・フロム・ユア・アイズの無言のメンバーみたいなものさ」
しかし、最初のシングル「ライフ・サインズ」は、本格的なライブバンドのダイナミクスを基に形作られました。「バンドと演奏する時は、そのバンドを念頭に置いて曲を書くものだけど、これはWFYEのために、地下室よりも大きな場所で演奏するのを想像して書いた初めての曲だ」と彼は指摘します。
「Nights In Armor」は、フリスチャンテのストラトキャスターの至福の渦で始まる。『Born 2』は世界観を構築するギターのアタックで、ブラウンの声が上空を滑るように響く歌詞は、SF文学と政治理論への執着を反映している。
「世界はそれほど普通で / 別の何かに生まれ変わるために存在する。私は『The Dispossessed』(ウルスラ・K・ル・グインの1974年のアナキスト的ユートピア小説)と『There Is No Unhappy Revolution』(マルチェロ・タリの2017年のノンフィクション)をバックパックに入れて、1年以上持ち歩いている」とブラウンは語る。
「これらの本は4つの異なる大陸とほぼすべての州境を旅してきました。アルバムの歌詞を書く際、両方の本を徹底的に読み返しました」
『It’s A Beautiful Place』全体に、バンドが曲球をホームランに磨き上げた明確な感覚が漂う。迫りくるような悲しさと、驚愕と恐怖が交錯する。それは『ブレードランナー』に『WALL-E』の要素を添えたような、キューブリックとアシモフにジェイとサイレント・ボブの影を宿した世界だ。これらの曲は外の世界を見つめ、私たちの小ささを自覚し、宇宙における私たちの位置を問いながら、周囲の美しさを称賛する。
「Nights in Armor」