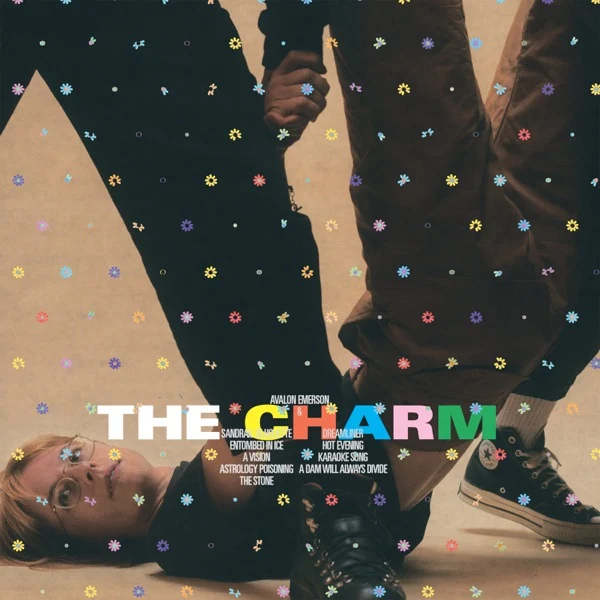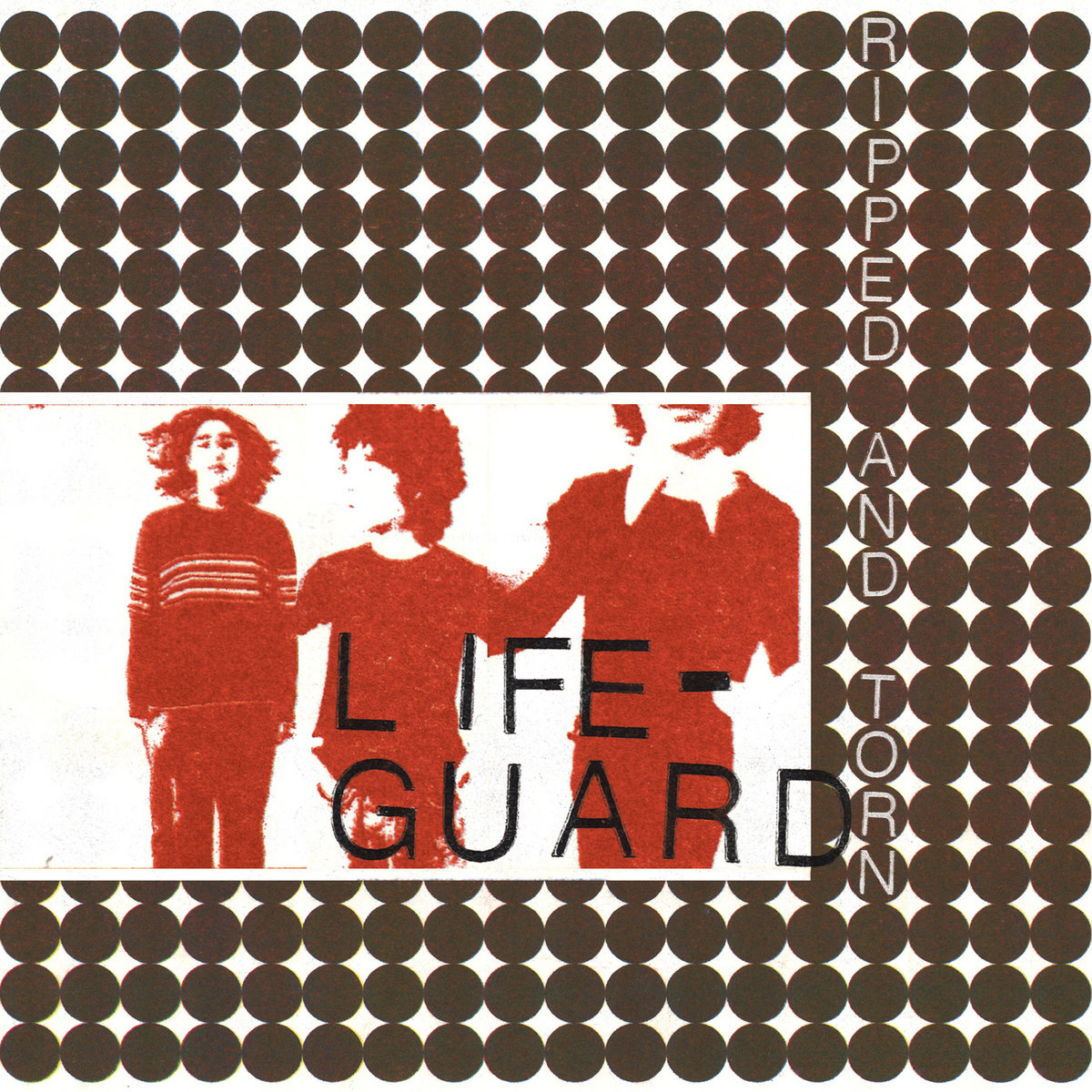サウスロンドンのヒップホップシーン
サウスロンドンは、既に、前にも記事で取り上げたが、ダブステップの発祥の地であり、またこのクラブミュージックが盛んな地域として知られているようです。
現在、サウスロンドンは、ヒップホップシーンが盛んな印象を受けます。元々、ロンドンのクラブシーンといえば、イーストロンドンが多くのアーティストが在住し、活動を行っている印象がありましたが、近年、このサウスロンドンにコアでホットなアーティストが数多く見られています。それほどヒップホップシーンには詳しくないけれども、サンファ、ストームジーらの台頭を見ても、サウスロンドンには魅力的なトラックメイカーが数多く存在します。
そして、現在においてもこれらのヒップホップアーティストは、ジャズ、ディープソウル、R&B,そして、サウスロンドンの地域的な音楽といえるダブステップを雰囲気を見事にラップの中に浸透させ、新たな潮流を形作るような音楽性が育まれているように思える。これからのヒップホップシーンの課題としては、こういった以前、ロックシーンが行ったようなミクスチャーという概念により、どこまでその音楽性に奥行きをもたせられるか。
もちろん、これらのアーティストは、エド・シーランやカニエ・ウェストといったビックアーティストのステージングのサポート・アクトを務めたり、と少なからず関係を持っているが、その音楽性については似て非なるものがある。特に、これらのサウスロンドンのアーティストは、ヒップホップという音楽にジャズ、ディープソウル的な洗練性を加えて、比較的落ち着いた雰囲気のトラック制作を行っている。そこにはIDMといった電子音楽の要素も少なからず込められているような雰囲気もあって面白い。つまり、無節操というわけではないが、近年のサウスロンドンのヒップホップは様々な他のジャンルを取り入れるのがごくごく自然なことになっているように思えます。
これは、これらのヒップホップアーティストの音楽が付け焼き刃なものでなく、なんとなく、このサウスロンドンに当たり前のように満ちている音楽がこういったトラックメイカーの素地を形作っている様子が伺えます。また、サンファのように、ポスト・クラシカルのピアノ曲を取り入れていたりするのもかなり興味深い特徴。直近では、アメリカでは、カニエ・ウェストや、ドレイク(Jay-Zをゲストヴォーカルに迎えた)と、ビックアーティストの新譜も続々リリースされていて目が離せないラップというカテゴリ。そして、アメリカのヒップホップと並んで、イギリスのサウスロンドンは、特にクラブシーンが熱い地域で、ヒップホップフリークとしても要チェックでしょう。
Loyle Carner
そして、 サンファ、ストームジーに続くサウスロンドンの期待のトラックメイカーが、ロイル・カーナー。まだ二十代半ばにも関わらず、大人の雰囲気を持った、また精神的に進んだ人格を感じさせる秀逸なヒップホップアーティストです。特に、世界的に見て、最も有望株のヒップホップシンガーと言っても差し支えないはず。
 "Loyle Carner 1" by Stéphane GUEGUEN - Capo @ HiU is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
"Loyle Carner 1" by Stéphane GUEGUEN - Capo @ HiU is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
ロイル・カーナーは、幼少期からADHDとディスクレシアといった症状を克服しようとたえず格闘してきた人物。そのため、中々、子供の時代から学校の勉強に適応しづらかったようではあるが、後には、アデルやワインハウスを輩出したブリットスクールで音楽を学んでいます。
2013年に、Rejjie SnowのEP作品「Rejovich」収録のトラック「1992」に共同制作者として名を連ねたところから始まる。この作品で一躍、ロイル・カーナーの名はラップシーンの間にまたたく間に浸透して行きます。
また、翌年、ロイル・カーナー、ソロ名義の作品として、シングル「A Little Late」を自身のウェブサイトで発表し、大きな話題を呼びました。また、同年には、ケイト・テンペストとの共同制作、7inch「Guts」をリリース。続いて、マーベリック・セイバー、トム・ミッシュとコラボレートした作品を発表して、徐々に、英国のヒップホップシーンにおいて知名度を高めていくようになります。
英国国内でのツアーを成功させた後は、コンスタントにシングル作をリリースしていき、2017年にはスタジオ・アルバム「Yesterdays Gone」を発表。この作品は、2017年度のマーキュリー賞にノミネートされています。次いで、2019年には「Not Waving,But Drowing」をリリースして大きな注目を集めました。これまでのキャリアにおいて、ブリット・アワーズにもノミネートされている英国のクラブシーンで最も旬なアーティストと言えそうだ。さて、今回は、サウスロンドンの期待の新星、ロイル・カーナーのこれまでのスタジオ・アルバム二作の魅力について触れておきましょう。
Yesterday's Gone
TrackListing
1.The Isle Of Arran
2.Mean It In the Morning
3.+44
4.Damselfly
5.Ain't Nothing Changed
6.Swear
7.Florence
8.The Seamstress
9.Stars&Shards
10.No Worries
11.Rebel 101
12.NO CD
13.Mrs C
14.Sun Of Jean
15. Yesterday's Gone
一躍、ロイル・カーナーの名を、英国のヒップホップシーンに知らしめた鮮烈的デビュー作。「Yesterday’s Gone」は、古典的なイギリスのヒップホップの旨味を引き継いだ作品といえる。
リードトラックの「The Isle Of Arran」は、普遍的な輝きを持ったヒップホップの名曲と言っても誇張にはならないはず。
ここで、展開される軽快なライムの爽快感、そして、そこにディープ・ソウルの音楽性が見事な融合を果たしている。この辺りは、ワインハウスを輩出したブリットスクール出身のアーティストらしい感性の鋭さ。しかも、自分のライムが首座にあるというより、彼自身は引き立て役に回り、英国発祥のディープ・ソウルをトラックメイクの主役に持ってきている辺りが秀逸。ディープ・ソウルに対するリスペクトが込められている。
興味深いのは、「Ain't Nothing Changed」では、ジャズとヒップホップを巧緻に融合させた見事なトラックメイキングが行われている。普遍的なヒップホップの軽快なライムに加え、サックスの芳醇な響きがサンプリングとして配置される。その合間に繰り広げられるカーナーの生み出す言葉のリズム感には独特の哀愁が漂っている。そして、トラックの最終盤では、ジャズに対し、主役の座を譲るあたりもトラック全体に奥行きをもたらす。平面的なヒップホップでなく、立体的な音の質感とアンビエンスを演出することに成功している。
特に、このデビュー作「Yesterday's Gone 」の中で全体な印象に最もクールな質感をもたしているのが、「The Seamstress(Tooting Masala」。ここで、ロイル・カーナーは、クラブシーンのコアな音楽性の領域に挑戦している、アシッドハウス、チルアウトに近い雰囲気を持ったトラック。ヒップホップバラードと呼べるような、独特な哀愁が漂っており、これまでありそうでなかった清新な雰囲気が滲んでいる。
カーナーのスポークン・ワードというのは、一貫して落ち着いており、気分が抑制されており、徹底してひたひたと同じ音程の間を漂っている。
どのトラックの場面においても、彼は、このスタイルをストイックに貫いている。それは独特な、波間を穏やかにたゆたうかのような情感をもたらす。ロイル・カーナーのライムの独特な雰囲気に滲んでいるのは、ヒップホップ音楽としての深い抒情性、ただならぬエモーションである。
また、その一種の冷徹さの中に、キラリと光る原石のような質感が込められていると思えてならない。特に、カーナー独特なライムとしてのリズムの刻み、Aha、といった間投詞が特に他のラッパーと異なるダウナーな印象を与え、語法にクールさをもたらしている。
このカーナー独自の要素、あるいは、スポークンワードとしての語法は、二作目のライムにもしっかりと引き継がれている。つまり、カーナーという人物、ひいては彼の音楽性の中核を形作っている。純粋に、フレーズの合間に出来た空白の中に、頷き一つをそつなく込めるだけで、トラックに、グルーブ感とタイトさをもたらし、アンニュイな抒情性を与えもし、さらに、それを徐々に渦巻くように拡張していく。しかし、それは徹底して内省的、つまり内向きなエナジーに満ちている事が理解出来る。カーナーは、このデビュー作においてこれまでありそうでなかったラップスタイルを生み出した。このロイル・カーナー特有の語法はほとんどお見事としか言うよりほかない。
「Not Waving,But Drowing」
TrackListing
1.Dear Jean
2.Angel
3.Ice Water
4.Ottolenghi
5.You Don't Know
6.Still
7.It's Coming Home
8.Desoleil(Brilliant Coners)
9.Loose Ends
10.Not Waving,But Drowing
11.Krispy
12.Sail Away Freestyle
13.Looking Back
14.Carluccio
15.Dear Ben
そして、ロイル・カーナーの完全なる進化、トラックメイカーとしてただならぬ才覚の迸りを感じさせるのが二作目のスタジオ・アルバム「Not Waving,But Drowing」。UKのアルバムチャートでは最高3位を、そして、R&Bチャートでは堂々1位を獲得している。
リードトラック「Dear Jean」は前作の流れを受け継いだ作品で、彼特有のスポークン・ワードのリズムがクールに紡がれている。どことなくジェイムス・ブレイクの音楽性に対する憧憬のも滲んでいるように思える。また、そして、前作よりも落ち着いた哀愁が漂う。
今作の中で最も聞きやすいと思われるトラックは「Ottolenghi」。ここではエレクトリック・ピアノをフーチャーしたR&B寄りのバラードが軽快に展開される。しかも前作よりもカーナーのスポークンワードはパワーアップし、よりラッパーとしてのハリと艶気が漂う。
特にこのアルバムで個人的に最も気に入っているトラックは、Samphaとの共同作品なっている「Dersoleli(Blilliant Corners) 」。
このトラックでは、サウスロンドンらしいダブステップの雰囲気とディープ・ソウルが見事な融合を果たしている。どことなく、憂鬱さを漂わせるピアノのアレンジメント、そして、この作品に参加している二人のラッパーの声質も絶妙にマッチしている。全体的に カーナーのスポークンワードは切れ味が鋭さを持つが、やはり、一作目のように徹底に抑制が取れたクールな雰囲気が漂う。そして、痛烈なエモーションな質感によって彩られている。この切なさは何だろうか? いかにもサウスロンドンという感じで、アンニュイな夜の空気感にトラックは彩られていて、異質なほどの艶気を漂わせている。リズムトラックも低音のバス、高音域のタムの抜けのバランスが心地よい。アウトロの爽やかに鼻で笑い飛ばす感じも、クールとしか言いようがない。
また「Krispy」は、ミニマリストとしてのサンプリングが際立つ爽やかな楽曲、終盤にかけてはジャズとヒップホップの融合に挑戦している。トランペットのジャズ的なフレージングも豪奢な感じに満ちている。特にアウトロにかけての独特な雰囲気はほのかな陶酔感によって彩られる。
全体的な作風としては、前作よりも落ち着いたディープ・ソウル寄りの渋めのヒップホップ。そして、なんと言っても、このスタジオアルバムが素晴らしいと思うのは、新たなヒップホップの可能性というのが示されていることだろう。ここではロンドン発祥のディープ・ソウル、ダブステップ、ジャズを見事にかけ合わせ、それを絶妙にブレンドしてみせ、更にこのジャンルの未来型を見事に示してみせた痛快な作品である。
特に、ラストトラックは、次の作品への序章のようなニュアンスを感じさせ、何かしら未来への希望に満ち溢れている。
つまり、まだ、この素晴らしいヒップホップアーティスト、ロイル・カーナーの壮大な物語は始まりを告げたばかりであることを示しているように思える。イギリスの音楽メディアが彼を「ヒップホップ界のホープ」と呼びならわすのには大きな理由があり、彼のスポークンワード、トラックメイク自体がそのことを、なめらかに物語っている。