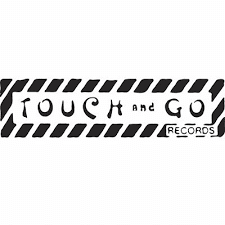ガレージロックの魅力
2000年代から、再びニューヨークのロックバンドがこぞってこのガレージロックを取り上げて、一躍脚光を浴び、その一連のムーブメントはガレージロックリバイバルというように名付けられた。
アメリカでは、ストロークスやホワイトストライプ、ヤー・ヤー・ヤーズを初め、イギリスでも同時代にガレージ・ロックの音楽性を引き継いだロックバンド、リバティーンズ、もしくは最初期のアークティック・モンキーズもプリミティヴなガレージロックサウンドを引っさげてシーンに台頭してきた。もしくはオーストラリアのダットサンズ、スウェーデンではハイヴズも出てきた。これは、一地域に限定されるものではなく、世界的なムーブメントであったように思える。
いかにも俺たちは昔のロックンロールを知っているという顔をしてクールに演奏するのがストロークスだったし、直情的に、60年代のプリミティヴなサウンドを引き継いで情熱的に演奏するのがハイヴズだった。日本のロックシーンで言えば、ミッシェル・ガン・エレファント、ブランキー・ジェット・シティ。インディーズ界隈でいうと、ギターウルフがこのジャンルに該当する。もちろん、ミッシェルのアベフトシさんは世界に通用する伝説的なギタリストの一人だった。
また、これらのロックバンドは、往年のロックンロールのコアな部分を受け継いでそれを洗練させただけで、新しいことはやっていないように思える。新しい音楽なんて洒落臭えという突慳貪さなのである。それにも関わらず、これらのガレージロックリバイバルのシーンを牽引していたバンドは、実際にライブパフォーマンスを見ると、どのバンドより輝いており、問答無用にステージパフォーマンスがカッコいいのは不思議でならなかった。(特に、ストロークスとハイヴズ)。ただ、ロックンロールを、寡黙に、朴訥に、演奏する、と言う面では、ラモーンズに近い雰囲気も感じられるようだ。つまり、ニューヨークのインディースタイルが色濃く感じられるジャンル。
ある程度このガレージロックの音楽性というのには限界があり、同じスタイルをながく続けて行くと、 聞き手も演奏者もそのうち飽きが来て、方向性の転換を余儀なくされることが多いのはいくらか仕方のないことかもしれない。(何十年も同じ音楽を続けていけるのはAC/DCだけの特権といえるかもしれない)しかし、それでもやはり、このガレージロックというのは、時代を越えて楽しめるロックンロールの本来の魅力が詰まっている音楽であることは間違いなし。
このガレージ・ロックっていうのは誰が始めたのか。このジャンルが流行るようになっていたのか、またどんな音楽性なのか、その大まかな概要を簡単に説明しておきたい。大まかに言えば、一般的にその先駆者は、アメリカのワシントン州のロックバンド、ザ・ソニックス、また、ミシガン州のザ・リッターから始まったムーブメントで、1965年前後に、その発祥が求められる。
ガレージロックの音楽性
ガレージロックというのは、アメリカのガレージ、車を止めておくスペースで、めいめいの機材を持ち寄り、アンプからフルテンのどでかい音量でロックンロールを奏でるというスタイルだ。フルテンというのは、アンプリフターのメーターをすべてフルに回し、音作りもへったくれもない素人感丸出しのすさまじい爆音サウンドが生み出される。そして、ガレージロックという語源は、そのままの意味で、ガレージで演奏するロックだから、ガレージロックと呼ばれる。
もちろん、これらの最初期のガレージロックバンドは、演奏自体の荒々しさという点においては、最初期のパンクロック、ロンドン、ニューヨーク・パンク勢との共通項も見いだせるようだ。その音楽性についても、六十年代らしく、ビートルズ、ストーンズサウンドに対する傾倒も伺える。つまり、シンプルなロックンロール性がその内郭に宿っている。代表格のザ・ソニックスやザ・リッターの音楽性には、アメリカのブラックミュージックの影響も色濃く滲んでいる。
そして、ビートルズとは全く異なる雰囲気がある。これらのガレージ・ロックバンド、とくに、ザ・ソニックスの演奏から醸し出される異様な熱気、すべてをなぎたおしていくようなパワフルさが、こういった直情的なロックンロールが展開されているので、聞き手にスカッとするような痛快味を与える。すなわち、これがガレージロックの最大の醍醐味といえるのである。このガレージのような場所で演奏する独特なスタイルはのちシアトルのグランジ界の大御所、メルヴィンズも積極的に行っていたが、やがて、90年代の”ストーナー”というアメリカの砂漠地帯で発生した男臭くワイルドなロックンロールに引き継がれていく。(Kyuss,Fu Manchuなどが有名)
この60年代のガレージ・ロックというジャンルは、いかにもインディペンデント形態で活動を行うロックバンドが多かった。
ソニックス、リッターズを始め、リトル・リチャーズやチャック・ベリーの最初期の踊れるロックンロールの原始的な音の雰囲気を受け継ぎ、それを耳をつんざくような大音量で奏でるというスタイルが徐々に確立されていくようになる。のちの音楽シーンのように、どこどこの地域で広がりを見せていったわけではなく、このガレージロックのスタイルを掲げるバンドがそのアメリカ全体に裾野を広げていったのではないだろうか。その過程において、MC5のようなアングラな人気を誇るガレージロック勢も出てくるようになる。これらのロックバンドに共通するのは、パンクロックに近い荒削りなサウンドを掲げ、分かりやすい形でオーディエンスに提示するというスタイル。
ここで、そもそもガレージロックというのが、完全なインディームーブメントの土壌の上に築かれたコアな音楽のムーブメントであったのか? そして、メインストリームではこういうプリミティヴな質感を持つロックンロール音楽はまったく存在しなかったのか? という二つの疑問がおのずと浮かんでくる。しかし、この疑問についてはある程度否定しておかなければならない。実は、著名なロックバンドにも、ガレージ・ロックに近い雰囲気を持った楽曲は数多く存在していた。例を挙げるなら、ジミー・ペイジやエリック・クラブトンが在籍したヤードバーズも、ガレージロックに近い雰囲気を持ったロックンロールを演奏していた。またローリング・ストーンズの「(I Can't Get No)Satisfaction」ビートルズの「Helter Skelter」には、ガレージ・ロックに比する荒々しさ、轟音性が見られることからも分かる通り、実は、結構メインストリームにいるミュージシャンは当たり前のように、こういったプリミティブな質感を持つガレージロック風の音楽性を、ガレージではなくリハーサルスタジオで好んで演奏していたように思える。
そして、ガレージロックという音楽は、Mainstream=主流ではなく、Alternative=亜流的な雰囲気を擁したジャンルとして、音楽通の間で、長年、しぶとく地下で生きながらえていたように思える。そして、ニューヨークのザ・ストゥージズ、ジョニー・サンダース・アンド・ハートブレーカーズも、このあたりのジャンル性を引き継いだ音楽で一世を風靡したものの、一時期、他のジャンル、ハードロック、メタル音楽が世界的に優勢になっていくにつれて、このガレージロックというロックンロールの申し子は、ロックンロール愛好家の間においても忘れ去られてしまったように思えていた。ところが、イギリスのザ・リバティーンズ、あるいは、スウェーデンのザ・ハイヴス、アメリカのザ・ストロークスの台頭を筆頭にして、それがロックンロールというジャンル自体が行き詰まりを見せていた1990年代、00年代、見事にガレージロックは復活を果たした。それからの流れについては多くの人がご存じであろうと思われる。まるで堰を切ったかのように、世界的にこのジャンルを引き継いだアーティストがドッと台頭してくるようになったのである。このリバイバルシーンの流れは音楽メディアによって、ガレージロックリバイバルと称された。
ガレージロックの名盤選
The Sonics
「Here Are The Sonics」
ザ・ソニックスは、ワシントン州で結成されたガレージロックバンド。ガレージロックの創始者として知られている。このソニックスの原始的なサウンド、そして、荒削りな演奏、ソウルフルな音楽性、さらに、つんざくようなハイテンションサウンドにすべてのガレージロックの源流は求められる。
特に、ザ・ソニックスのデビュー作「Here are The Sonics」1965は、ガレージロックの金字塔として名高い伝説的なアルバムである。
ここで展開されるプリミティブなサウンドの凄みは言葉に尽くしがたい。チャック・ベリーやリトル・リチャードのロックンロールをそのまま復刻したような音楽性に陶酔すら覚えるはず。一曲目の「Witch」から、とんでもないテンションロックンロールが目くるめく速さで通り過ぎていく。この圧倒的な迫力による痛快感は、遊園地のジェットコースターの刺激性など足元にも及ばない。
ディストーションをてきめんにきかせたギターのすさまじいど迫力、タムのハイエンドが強調されたしなるようなドラムの切れ味、さらに、ジェリー・ロスリーのソウルフルな渋みのあるボーカルもめちゃくちゃ良い。また、「Wah!!」というこぶしのきいた叫び、ここには、なんとも言えない若さゆえのみずみずしい魅力が詰まっている。しかし、ソニックスの本来の魅力は、若さによる外向きのエナジーだけにとどまらず、音楽面での年齢不相応の内面的な渋みが込められていることを忘れてはいけない。バンドサンドの中に、ちゃっかりサックスフォン、エレクトーンを取り入れているのも、若いロックバンドとしてはあまりに渋い特徴である。この音楽性が、現在でもソニックスを現役のロックバンドとして息の長い活動を支えているのだ。また、それに加え、ギターの癖になるようなフレージング、ぶんぶん唸るベースの厚み、そう、ここに録音されているすべてが、ロックンロールとして完璧!と言って良いのかもしれない。
もちろん、ザ・ソニックスの魅力は、楽曲そのものの痛快さ、若さゆえの無謀にも思えるハイテンション、それらをぐいぐい引っ張っていくリズム隊、バンドサウンドの力強さにある。これは、アメリカのガレージで行われた壮大なロックンロールパーティー。未熟さというのを臆面もなく前面に押し出し、それを輝かしい音で見事に刻印してみせたガレージロックの傑作なのである。
ザ・ソニックスは、アンダーグランドシーンの代表的なバンドとして世に膾炙されているが、その後のインディーシーンに多大な影響を及ぼしたロックバンド。魂のこもった本来のソウルの申し子としてのロックンロールの要素が詰められた伝説的な作品。とくに、新旧問わず、ロックファンとしては、このアルバム収録「Do You Love Me」「Psyco」 「Roll Over Beethoven」は聞き逃せない。
The Kinks
「Kinks」
イギリスのロックバンドとしては、ビートルズやストーンズ、ザ・フーの次に大きな人気を誇るザ・キンクス。
意外にも初期にはガレージ・ロックバンドに近い質感のある荒々しいロックンロールを奏でていることには驚嘆するよりほかなし。特に、このキンクスの鮮烈なデビュー作「The Kinks」で聴くことの出来るプリミティヴな音楽性は明らかにガレージ・ロック寄りの雰囲気を滲ませている。特にアルバム全体のギターのサウンド処理がギターという楽器の原始的な響きを重視しているため、いかにもソニックにも近い原始的なロックンロールの魅力を余す所なく体現している。
ザ・キンクスの代名詞、ロック史において名曲に挙げられる「You've Really Got Me」は、シンプルかつソリッドなロックンロールとして知られる。しかし、驚くべきことに、キンクスはソニックスより一年早くガレージ・ロックサウンドを確立させている。他にも「Revenge」のイントロを聴くと、スタンダードなロックというよりか、ガレージ・ロックの雰囲気が感じられる。
ロック史の名盤としてのみならず、ガレージロックの名盤としても挙げられることが多い今作。ストーンズに比べると軽視されがちなロックバンドではあるが、実は、ロック史を概観してみたとき、後のブラーといったイギリスのロックバンドの本流の重要な音楽性を形作っている。
The Litter
「Distortion」
ザ・リッターは、1966年に結成されたミネソタ州ミネアポリスの五人組ガレージロックバンド。
ガレージロックの祖、ザ・ソニックスに比する原始的なロックンロールサウンドが魅力。特にデビュー作「Distortion」は、ガレージロック隆盛の時代の勢いを時代的に刻印してみせた傑作。
ここではエフェクター「ビックマフ」のような苛烈なディストーションサウンドが体感できる。そして、なんと言っても、このザ・リッターの魅力は、痛快なビートルズやザ・フー直系のプリミティヴなロックンロールテイストにあり。ロックンロールとしてもひしゃげていてめちゃくちゃカッコいい。
特に、コーラス・グループとして、又は、極上のポップスとしても充分たのしめるような雰囲気もある。オリジナル曲「Whatcha Gonna Do About It」のノリの良い痛快なロックンロールも素晴らしく、ここにはザ・フー、イギリスのモッズシーンに対する憧憬も存分に込められている。
ザ・フーのカバー、「Substitute」。それからなんと言っても、「Legal Matter」はかなり秀逸なアレンジメント。この若々しく、みずみずしく、ちょっとだけ切ないような青春の響きは、ガレージロックとしてでだけはなく、パワー・ポップあたりの音楽性との共通点も見いだされるはず。また、ベルベット・アンダーグラウンドの中期の方向性のようなソリッドな荒削りさも持ち合わせている。六年間という短い期間で解散したロックバンドであるものの、ザ・ソニックスとは異なる魅力を持つ、ザ・リッター。隠れた名ロックバンドとしてここで御紹介しておきたい。
The Velvet Underground
「White Heat/White Light」
所謂、アンディー・ウォーホルととの関係性上において語られることが多く、なおかつニューヨークのオルタナティヴバンドの始祖として語られることの多い、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド。
しかし全体的なロックバンドとしての印象は、現代のアートポップの先駆者といえるのかもしれない。その固定的なアートのイメージに比べ、「Sunday Morning」「Sweet Jane」等の歴代の代表曲を見ても分かる通り、意外にポピュラーの要素が強いロックバンドであるように思える。これは、ルー・リードがいかに傑出したソングライターであるかのを証立てているように思える。
一般的なロックバンドとして評価される一方で、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドは、パンクロック/ガレージロックのアングラな流れを最初に形作ったと見なされることもある。一例を挙げるなら、デビュー作「The Velvet Undergoround」においては「European Sun」「Heroin」に代表されるように、この1960年代でプリミティブな退廃的なロックンロールを既に完成させている。
デビュー作の翌年リリースされた二作目の「White heat/White Light」は、ガレージ・ロックの名盤として挙げておきたい原始的なロックンロールの魅力を体現した一枚である。特に、表題曲「White heat/White Light」この一作目とは打って変わって、粗削りでプリミティヴなロックンロールサウンドに回帰を果たしている。また、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの影の名曲として語り継がれている「Sister Ray」は、ガレージ・ロック本来の響きを収めた17分半の歴史的超大作である。そして、この楽曲のロックンロールバンドとしてのアバンギャルド性、最終盤の狂気的なすさまじい迫力にこそ、ガレージロック、ひいてはロックンロールの醍醐味が詰めこまれているのだ。
この「Sister Ray」という一曲が後世のロックシーン、2000年代の、ストロークス、リバティーンズといったリバイバルシーンのアーティストの創作性に与えた影響というのは凡そ計り知れないものがある。最も有名なファーストアルバムだけで、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの本来の魅力は掴みきれるというわけではない。正に、この二作目にこそヴェルヴェット・アンダーグラウンドの本当のロックバンドとしての超絶性が刻印されている。そして、この伝説的な作品は、いかにロックンロール音楽が芸術的であり、素晴らしいものであるのかを見事に物語っている。
MC5
「Kick Out The Jams(Live)」
The Stooges
「the stooges」
ザ・ストゥージズは、MC5と同じように、工業都市デトロイトから出発した、ミシガン大学で、イギー・ポップを中心に結成された伝説的な四人組ロックバンドである。このロックバンド、ザ・ストゥージズの解散後、このバンドの中心人物、イギー・ポップは、のちにデヴィッド・ボウイ等、世界的なスターミュージシャンとも関わりを持ち、イギーは、彼等二人に比する存在感を持つようになる伝説的なロックミュジシャンとなった。ソロ活動としては、結構、「Lust For Life」を始め、ポップスに近い雰囲気をもった楽曲のイメージがまとわりつくロックミュージシャンである。しかしながら、イギー・ポップの本質的な音楽性はやはり、このデトロイト時代、ザ・ストゥージズにおけるデンジャラスでプリミティヴなガレージロックに求められる。
とりわけ、このストゥージズのデビュー作品 「the stooges」は、のちにジョン・ケイルやデヴィッド・ボウイがリミックスを手掛けた歴史的名盤。後の「Raw Power」と共に、パンクロックの祖といわれる伝説的な名盤。また、ニューヨークに最初にガレージ・ロックを呼び込んで見せたイギー・ポップのデビュー作にして代表作である。
特に、アルバムの一曲目「1969」で展開されるガレージ・ロックの原始的な輝きは未だに失われていない。このワウを噛ませたギターサウンドの渋みは一聴の価値あり。続く「I Wanna Be You Dog」もギターサウンドの面でガレージロックらしいディストーションの轟音性を味わうことが出来る。
そして、後のイギー・ポップの狂気性、獰猛性、すさまじいハイテンション性の萌芽もここにうっすらとであるものの見うけられる。一方、ここでは、きわめてその性質とは対照的なクールなイギーの雰囲気も感じられる。それから、なんといっても、ガレージロックの一番重要な要素、ディストーションで歪みに歪んだロックンロールの危うさが、この作品ではシンプルに端的に提示される。以後の作品「Raw Power」「Fun house」では、サイケデリックロック、パンクロックと次の領域に踏み込んでいったストゥージズ。しかし、この鮮烈なロックンロール性を提げてシーンに華々しく登場したデビュー作にこそ、このロックバンド、ひいてはイギー・ポップの最大の醍醐味、荒削りなガレージ・ロックの元祖としての魅力が存分に詰め込まれている。
Johnny Thunders&The Heartbreakers
「L.A.M.F」The Lost '77 Mixes
ジョニー・サンダースは、ロンドンパンクスのジョニー・ロットンに比べ、コアなファンをのぞいては、それほど一般的な知名度を持たないロックミュージシャンである。
もちろん、サンダースの人生の最期が、何かしら彼のイメージに暗い影を落としている側面もなくはないのかもしれない。
それでも、元は、ニューヨーク・ドールズのメンバーとして活躍していたニューヨークシーンの名物的な存在、ジョニー・サンダースは、その全生涯の短さにも関わらず、いや、その生涯の短さゆえ、後世の音楽に大きな影響を及ぼした偉大なロックミュージシャンである。もちろん、このハートブレーカーズ、ジョニー・サンダースがもしかりに存在していなかったとしたら、セックス・ピストルズどころか、ロンドン・パンクすらこの世に生まれ出なかった可能性もある。それくらい、ロックンロール性を生涯において体現した素晴らしいミュージシャンなのだ。
ソロ活動では、穏やかでやさしげな一面を覗かせるフォークロック寄りの音楽を奏でるジョニサンであるが、ハートブレーカーズとしてのリリースされた「L.A.M.F」は、引き締まった捨て曲のないロックンロールの旨味を抽出したような名作。もちろん、後世のロックンロール、ロンドンパンク、ガレージロックと多岐に渡るジャンルの橋渡しのような役割を果たしたロック史からみて最重要の名作と言える。
「L.A.M.F」。
あらためて、この伝説的なアルバム全体として捉え直してみると、スタンダードなR&B色の感じられる、実に軽快なロックンロールの珠玉の名曲ばかりがずらりと並ぶ。特に、「Going Steady」「Do You Love Me」「Born to Lose」といったロックンロール史に燦然と輝く名曲は、ニューヨーク・ドールズ時代の音楽性を受け継いでおり、今、じっくり聴いてみると、たしかにロンドン・パンクの音楽性の萌芽も見えなくはないにしても、実は、ド直球のガレージ・ロックとしても楽しめるプリミティブな魅力を持つロックンロールナンバーがずらりと並べられている。
あまりに、大きな影響を後世のロック史に与えてしまったためか、ジョニー・サンダースの生涯は38年と余りにも短かった。
いや、それでも、もちろん、サンダースの破天荒でデンジャラスな生き様を手放しで称賛するわけではないのだけれども、誰よりも、太く短く、逞しく生きたのがジョニー・サンダースというミュージシャンだった。これぞ、まさしく、最もクールなロックンローラーらしい生き様ではないか。