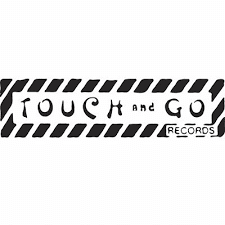Touch and Go Records
米、イリノイ州シカゴに本拠を置くレコード会社「TOUCH&GO」は、歴史のある老舗インディーレーベル。元々、独立ファンジンを発行していたテスコ・ヴィーとデイヴ・ステムソンにより1981年に設立されました。
このレーベルは、ニューヨークの「Matador」、シアトルの「Sub Pop」と共に、1980年代から米国のインディーズの音楽シーンを牽引してきた存在といえるでしょう。
イギリスの名門レーベル「ラフ・トレード」「4AD」と同じく、その影響というのはアンダーグラウンドシーンにとどまらないで、メインストリームのミュージックシーンに新鮮な息吹をもたらしたレコード会社です。
レーベル設立当初の最初期の1980年代は、Necros、Die Kreuzen、Negative
Appriachを始め、ハードコアパンクバンドのリリースを主として行っていましたが、徐々にアーティストの方向性を広め、多岐に渡るジャンルの作品リリースを推進していくようになります。
このインディーレーベルの主な功績としては、ポストロックというジャンル概念を生み出したことにあります。
二千年代から、世界的に流行るようになったPost RockーMath Rock(”数学的”で複雑な音楽構成をなすことから、この呼称が付けられた)というジャンルの概念を生み、その近辺の音楽性を持つアーティストを、いち早く世に送り出していったのがタッチ・アンド・ゴーなのです。
その後、1990年代に入ってから、シカゴ界隈の音楽シーンは盛り上がりを見せ、様々な人種の織りなす多種多様な文化概念を反映したミュージックシーンを形成していく。
元々このシカゴという地域がハウス・ミュージックの発祥で、ニューオーリンズのように、音楽そのものが街の生活の一部として染みついているからこそこういったシーンが生まれたのでしょう。
その後、1990年代から2000年代に差し掛かり、シカゴ音響派という造語も出来、音楽の聖地としてのシカゴ、そんなふうに呼び習わしても言い過ぎでない流れが出てくるようになりました。
この四十年にも及ぶ「Touch and GO」のリリースカタログから見いだせる特徴は、パンク、オルタナティヴ、ダンス、ポストロック、マスロックといったコアなミュージシャンを輩出するにとどまらず、Battlesの前身Don Cabalello、TV on the Radio、Yeah Yeah Yeahs、Blonde
Redhead、というように世界的な知名度を持つメジャーバンドも続々とシーンに送り出し続けています。
そもそも、このタッチ・アンド・ゴーは、才覚ある若手バンドの潜在能力を見抜くスカウト能力が、他のレーベルに比べて抜群に際立っていて、荒削りでありながら異彩を放つ若手アーティストを積極的に発掘して、作品リリースを重ねながら育てていくというのがこのレーベルの特色です。
2000年代に入り、経営難に陥り、2009年には新たなリリースを停止しているのは残念ですが、米国のミュージックカルチャーの土壌を耕し、育て、盛り上げていくコーチ的役割も担ってきたのがタッチアンドゴーの偉大さです。是非、中古レコード屋、あるいは気に入った作品があれば、購入してもらいたいと思います。今後のレーベル運営のモチベーションとなるはずです。
今回、個人的に強い思い入れのある「Touch and Go」の四十年近いレーベルの歴史の中から、選りすぐりの名盤をいくつかピックアップしていきましょう。
Touch And Go Recordsの名盤
Slint
「Spiderland」 1991

この作品は、タッチアンドゴーレコードの代表的な名盤というに留まらず、ミュージックシーンを完全に塗り替えてしまったといえる歴史的な名盤。
驚くべきなのは、この数奇な音楽が、十代の少年たちが家のガレージで長年にわたりジャムセッションを胆力をもって続ける上で生み出された青春の産物であるということ。
この後、無数のポストロック、マスロックのフォロワーを生み出していながら、彼等の存在を超えるアーティストはいまだ出てきていない。気の遠くなるような時間を音楽のミューズに捧げつくしたからこそ生まれた必然の産物といえ、学業やその他の学生生活、または恋愛に向けられるべき情熱を全て音楽に捧げた結果なのでしょう。
もちろん、この作品「spiderland」が音楽としてリリースされた頃には、スリントのメンバー四人は、ティーンネイジャーではなくなっていますが、アルバムの最後に収録されているロック史の伝説、英国の詩人、サミュエル・テイラー・コールリッジの詩に音楽をつけた「Good morning, captain」の構想は、彼等のドキュメンタリーを見るかぎり、十代の頃出来上がっていたものと思われます。
スリントの四人が湖で立ち泳ぎをしながら顔を突き出した写真というのも非常に印象的である。そして、その音楽性についてもきわめて先鋭的、個性的であり、どこから影響を受けて生まれ出たのかよくわからない。
ましてや、どういった意図を持って作られた音楽なのか解せないような作品が、たった四人のティーンネイジャーによって生み出されてしまうのが実に信じがたいものがあります。これは日本やイギリスといった土地では生まれ出ない、これぞアメリカといったロック音楽。これはまた、米国のガレージ文化が生み出したモンスターアルバム。
静と動の織りなす激烈な曲展開、そこにクールに乗せられる、一貫して冷ややかなポエトリーリーディングを思わせるボーカルスタイル。それが、曲の展開に、一瞬にして激情的なスクリームに変貌してしまうありさま。これはまるで、ルー・リードの時代に返ったかのような姿勢であり、時代の流行り廃りから完全に背を向けているからこそ、生み出しえた数奇な表現といえるでしょう。
さながら何十年もスタジオミュージシャンと務めてきたような風格のある職人的なタメの効いたドラミング、ノンエフェクトからの狂気的に歪んだギターのディストーションへの移行。そして、その土台を支えるきわめてシンプルなベースライン。これら三要素が一体となってがっちりと組み合わされているのがスリントの音楽性の特色です。
このアルバムには、その後のグランジムーヴメントを予見させるような雰囲気も滲んでいて、アメリカの表の音楽世界とはまたひと味ニュアンスの違った裏側の音楽世界が広がっている。
この作品が後世のロックミュージシャンに与えた影響というのは計りしれず、日本のToeやLiteといったポストロック、マスロックも、このバンドなしには成り立たなかった伝説的な存在。ポストロックの原型を形作ったのがスリントという数奇なロックバンドといえ、全ロックファン必聴の一作。
Don Caballero
「American Don」2000

ドン・キャバレロは、1991年、デイモン・チェを中心としてピッツバーグにて結成。のちのバトルスのギタリストとして活躍するイアン・ウィリアムズも在籍していたバンド。
このバンドの音楽というのは、アメリカのインテリジェンス性の飛び抜けて高い大学生が、数学的な頭脳を駆使し、実験的な音に取り組んだという印象。
キャバレロを聴くと、あらためて作曲をするのに最も必要なのは、数学的な才覚であると分かります。
ここには、後のバトルスの完成度高いダンスミュージックへの布石も感じられる。このバンドは、二千年代以降のポストロック・マスロックの流行りの型を作ったという功績は無視できず、音楽史に果たした役割というのは大きい。
ドン・キャバレロの作風としては、セッションの延長線上にあり、ジョン・アダムスやスティーヴ・ライヒが提唱した”ミニマル・ミュージック”(短い楽節を変奏を繰り返しながら展開していく楽曲の作風)の概念をさらに先に推し進め、それを現代的なロックの解釈としてアレンジメントした。
アナログディレイの機器に、ギターやベースからシールドによって配線をつなぎ、電子の弦楽器をシンセサイザーのような使用法をしている。そして、ベースの出音をあえて早めることにより、ドリルのような連続的クラスター音を発生させている。いかにも、その音の構成というのはシュトックハウゼンから引き継がれたものをロックでやってのけてしまったという革新性。
ディレイという装置の細かな時間のタイムラグをうまく駆使することにより、細かな音をつなぎわせ、アンビエントの境地にまで運んでいってしまったのが、このバンドの凄まじい特徴です。
このアルバム「American Don」は、ライブセッションのようなみずみずしい彼等の演奏が聴く事が出来、ひとつの完成形を見たという印象。ここでめくるめくような形で展開されるのはロックとしてのフリージャズ。
二曲目収録の「Peter Cris Jazz」は、彼等の美麗なメロディセンスが発揮された名曲。ここで繰り広げられるベースのドリル音のようなサウンド処理というのは音楽の革命といえるでしょう。
あらためて、ロック音楽の中には、知的なバンドも中には存在するのだという好例を、彼等はこの作品で見せてくれている。いわゆるミュージシャンの参考になるアーティスト、決して聞きやすい音楽性ではありませんが、既存のロックに飽きてしまった人には目から鱗と言える奇跡的傑作。
Big Black
「RICHMAN'S EIGHT TRACK TAPE」1987

ビッグ・ブラックは、オルタナティヴ界の裏の帝王ともいえる鬼才スティーブ・アルビニの激烈な宅録テクノ・ハードコアバンド。 のちに、アルビニがニルヴァーナの「イン・ユーテロ」の作品を手掛け、世界的なプロデューサーとなるのはまだ数年後まで待たねばならない。
さらに、そのまたのちに、ジミーペイジ&ロバート・プラントの作品のエンジニアをつとめるようになるなんて大それた話は、少なくとも彼の最初のミュージシャンとしての活動形態、このビッグ・ブラックを聴くかぎりでは全然想像出来ないでしょう。
ビック・ブラックの活動というのは太く短くといった表現が相応しく、スタジオ・アルバムを二枚リリースしているのみ、後はライブ・アルバムや、細々としたサイドリリースとなっています。
この「RICHMAN'S EIGHT TRACK TAPE」は、いわばビッグブラックのベスト盤的な意味合いのある作品。
この宅録ハードコアバンドの主要な楽曲を網羅し、そして、初期のレアトラックを集めた、スティーヴ・アルビニの若き日の音楽に対する情熱がたっぷりギュウギュウに詰まった作品。
この作品において見られる、古いMTR(マルチトラックレコーダー)の8トラックで、少ないトラック制限がある中、音を丹念に重ねて録音し、入念にマスタリングをしていくというきわめて初歩的なレコーディングの手法が、後のスティーヴ・アルビニの天才的エンジニアとしての素地、またその有り余るほどの鮮烈な才覚の芽生えが顕著に見えることでしょう。
ビック・ブラッグの音楽性についてはストイック、ハードコア・パンクを下地にしながらライムの風味すら感じられる硬派なギャングスターハードコア。精密で冷ややかなマシンビートが刻まれる中、のちのアルビニサウンドの原型をなす、硬質な鉄のようなギターサウンドの際立った存在感、そして、アルビニのすさまじい猛獣のような咆哮、奇妙な色気のあるシャウト、コテコテのお好み焼きのような要素がギュウギュウ詰めになっています。年若い、アルビニ青年のありあまるほどの音楽への情熱が感じられる、比類なきハードコア世界の深みを形成しています。
ここには、およそアメリカの最深部の音楽世界が深く充ち広がっており、その海底に入り込んだら抜け出せなくなるような危なっかしい魅力が満載。スティーヴ・アルビニのプロデューサーとして性格だけでなく、ミュージシャンとしての表情が垣間見える貴重な作品となっていて、このアルビニ・ワールドというのは、さらに、その後の彼の活動、RapemanからShellacの系譜へ引き継がれていきます。
Black Heart Procession
「Amore del Tropico」2002

40年という長きに渡るTouch and Goのリリースカタログ中でも、際立って風変わりなアーティストと呼べるBlack Heart Procession。カルフォルニアのサンティエゴ出身のロックバンドです。
このアルバムは、キャッチーでポップ性が高いとはいえません。しかし、それでも、ここには、独特なダンディーでクールな渋い漢の世界が広がっている。スパニッシュ風の音の雰囲気が心なしか漂っており、ブエナビスタ・ソシアルクラブやジプシー・キングスのような民族音楽、エスニック色が滲んだ渋みある作風です。
表題がイタリア語であることから、何かしら、名画「ゴッドファーザー」に対する憧憬も感じられ、イタリアンマフィアのダンディズムに満ちた世界観ともいうべき概念が音楽によって入念に組み立てられている。
また、ここには、一貫してストーリ性のようなものが貫かれており、映画のサウンドトラックの影響を感じる、SEのような楽曲もあり、映像シーンのひとこまを音によって印象的に彩るようなロックソングもありと、彼等の多彩な付け焼き刃でない音楽の広範なバックグラウンドが伺えます。
ブラック・ハート・プロセッションの曲調というのは、「Tropics of Love」をはじめとして、短調の曲が多く、明るさの感じられる作風ではありませんが、ここで展開されている癖になるリズムと、女性のバックコーラスの味わいは、独特な渋みが見いだせる。
名曲「The One who has Disappeared」では、古いトラッドなアメリカンフォーク、ジョニー・キャッシュを彷彿とさせる楽曲もあり、それほど知られていないバンドが、こういった良質な曲をさらりと書いてしまうあたり、アメリカの音楽文化の奥行き、ロックと言う音楽の幅広さ、深みのようなものを感じずにはいられません。
Blonde Redhead
「Melody Of Certain Damaged Lemons」2000

イタリア人兄弟、日本人移民カズ・マキノによって、NYで結成された前衛ロックバンド、ブロンド・レッドヘッド。
音楽性としては、ジャズ、ダンス、そして、古典音楽のエッセンスを織り交ぜ、ロック音楽として昇華しているのが主な特徴といえるでしょう。
彼等の楽曲の雰囲気は一貫してアンニュイで、女性らしからぬ激情性が感じられる辺りが、妖艶な華やかさをこのバンドの全面的な印象に添えています。
紅一点の女性ボーカル、カズ・マキノが、ライオット・ガールのように華やかなフロントマンとして君臨し、実験的、前衛的な不協和音を前面に押し出した音を奏でるという点では、同郷、ソニック・ユースに比するものがあり、彼等三人の音楽というのはメロディに重きを置いているのが特色。
通算五作目となるアルバム「Melody of Certain Damaged Lemons」は、次作からイギリスの名門「4AD」に移籍する直前の、最もブロンド・レッドヘッドの勢いのある瞬間を捉えた名作で、三人のこの後の音楽の方向性を明瞭に決定づけた作品でもあります。
ここに現れ出ているイタリアバロック音楽あたりからの色濃い影響を受けた性質はこの次の「Misery Is A Butterfly」でいよいよ大輪の花を咲かせます。
このアルバムは彼等の活動の分岐点ともいえ、最初期からのノーニューヨークを現代に蘇らせたような激しいノイズロック色の強い実験的な音楽、さらに、この後に引き継がれていく古典音楽からの要素が見事に融合しているのが際立った特徴でしょう。
ビートルズの「Because」を彷彿とさせる「Loved Despite of Great Faults」、古典音楽の影響を色濃く感じさせる「For the Dameged」。またその続曲「For The Damaged Coda」あたりに、カズ・マキノしか紡ぎ出しえない特異な詩情、男性のダンディズムと対極にある女性の”レディズム”ともいえる概念が引き出され、音楽史上において異質な輝きを放っています。
さらには、初期からのバンドの前衛性を引き継いだ「Mother」の激烈なクールさというのもニューヨークのバンドならではといえます。
また、近年のこのバンドの主な音楽性を形作っているダンス・ミュージック色の強い名曲「This is Not」。このファッショナブルな雰囲気のあるポップソングというのも聴き逃がせません。
TV On The Radio
「Desperate Youth, Blood Thirsty Babes」2004

その後、世界的な活躍を見せるようになるニューヨーク、ブルックリンの四人組バンド、TV on The Radioの鮮烈なデビュー作。
このバンドの音楽性の特徴というのは、ブラック・ミュージックをドリーム・ポップ的な雰囲気を交え、クールに解釈した辺りがみずみずしい輝きを放っています。
彼等の音楽は、ヒップホップとまではいわないまでも、近現代のソウルミュージックの奥深い音楽性をしっかりと受け継ぎ、現代的なポップ、ロックという形で表現。ブラック・ミュージック性を誇り高く打ち出して、ロックを新しい時代に推し進めた先駆的存在です。
このアルバムでは、実験的な音楽を奏でていますが、ここには、ダンスミュージックとして聴いても秀逸な魅力が感じられ、ボーカルのトゥンデ・アデビンペのボーカルスタイルの純粋なクールさというのも際立っています。
このアルバム二曲目に収録されている「Staring at the Sun」は、インディーロック史に語り継がれるべき名曲といえ、二千十年代になってMyspaceで愛好家の間で話題を呼んでいた楽曲。
シンセサイザーのベース的なフレージング、サンプラーのビート、ギターカッティング、また、このボーカルスタイルの洗練された革新性の空気が漂う。そして、このスタジオアルバム全体には都会的なスタイリッシュな雰囲気も漂い、そこが新鮮かつクールに感じられるはず。
Brainiac
「Electro Shock for President」1997

後、ダフト・パンクの築き上げたなSci-fiロックともいうべき、革新的なジャンルを打ち立てて見せたブレイニアック。
タッチアンドゴーのポストロック色の強いリリースからするとかなり異端的存在といえるでしょう。
このアルバムは、EP「Internationale」に比べ、より主体となる音楽性が明瞭となり、この後の方向性であるギターサウンドを前面に打ち出していき、音楽としてのSF色をさらに強めていくようになるブレイニアックの作風の契機ともなった重要な作品です。
翌年の名作「Hissing Pigs in static Couture」に比べ、ダンスフロアで鳴らされることを想定したような趣のあるクラブミュージックよりの音楽。
一曲目からUKのプライマル・スクリームの傑作、「Kill All Hippies」を彷彿とさせるエレクトロの楽曲からしてクールとしかいいようがなく、アメリカのバンドとして異質な雰囲気が滲んでおり、アメリカのクラブシーンというよりかは、UKのロンドンやブリストルのダンスフロアシーンに対しての反応、それをアメリカらしい多様性によって独特にアレンジしたような楽曲です。
「Flash Ram」に代表されるヴォコーダーを活用したクラフト・ヴェルクのドイツの電子音楽に対する現代的回答もあり、このあたりがブレイニアックのクラブミュージックに対する深い造詣が伺える。
「Fashion 500」 「The Turnover」では、グリッチに対する接近も見られ、一辺倒にも思える作品全体に非常に異質な、通好みにはたまらない雰囲気を醸し出すことに成功しています。
また、「Mr.Fingers」で繰り広げられるような荒々しいプリミティヴなガレージロック風味のあるブレイクビーツスタイルも、新しいジャンルを確立したといっても過言ではないはずです。
ここには、クラブミュージックとロックンロールを融合、それをさらに、未来に進化させたSci-fiロックの究極型がダフト・パンクとは異なるアプローチによって見事に展開されています。
YEAH YEAH YEAHS
「Yeah Yeah Yeahs」 2002

数々のミュージックアウォードの受賞実績を誇り、名実ともにタッチアンドゴー出身のバンドとしては一番の出世頭ともいえるヤー・ヤー・ヤーズ。
00年代からのガレージロックリバイバルのシーンの流れにおいて見過ごすことのできない最重要アーティストといえ、ストロークス、ホワイト・ストライプスの系譜にあるスタイリッシュなガレージロックバンド。
このデビューEPは、ヤー・ヤー・ヤーズのフレッシュな初期衝動が発揮された名作、彼等のその後の洗練された作品とまた異なるプリミティブな魅力がたっぷり味わいつくせるはず。
このロックバンドのとくに目を惹く特徴は、ライオット・ガールとしてフロントマンに君臨するカレン・Oのキュートな華やかさ、そして、ボーカリストとしての比類なき力強さにあるでしょう。
一曲目の「Bang」からして、フルテンの直アンから出力したような轟音ギターサウンド。往年のガレージロックバンド、The Sonicsを彷彿とさせるような、荒々しくプリミティブなド直球のストレートなロックンロール。
また、ここには、スリーピースバンドとしての音のバランスの良さ、そして、ベルヴェット・アンダーグラウンドやストゥージズから引き継がれるクールでスタイリッシュな音楽性を引き継いで、それがダンサンブルな掴みやすい楽曲として昇華されている。
四曲目収録の「Miles Away」は、往年のNYロックンロールの真髄を知る者にこそ生み出しうるヒットナンバー。「Art Star」は、カレン・Oがスクリーモに果敢に挑戦しているのも聞き所。
アルバム全体の雰囲気には、その後の彼等の華々しい活躍と成功が想像でき、そして、また、その後の完成形の萌芽といえる荒削りな音楽フリーク的な彼等の趣向を見いだせる。全編通して妥協なしの十三分。再生を始めると、嵐のようにヒットチューンが目の前をすまじい早さで通り過ぎていく。
Dirty Three
「Whatever You Love,You Are」2000

この名盤紹介において最後に挙げておきたいのは、オーストラリア出身の三人衆、ダーティー・スリーです。
タッチ・アンド・ゴー・レコードの四十年というリリースにおいて、レーベルの芸術的な性格を最も特色づけているアーティスト。
ギター、弦楽器、ドラムというトリオ編成で、弦楽器をジャズフュージョンのようにバンド編成中に取り入れた硬派で前衛派の音楽グループ。他のポスト・ロックバンドに比べ、彼等の音楽性の特異なのは、ドラムやギターが脇役であり、弦楽器のハーモニーが主役とはっきり主張している。
この後、スコットランドのモグワイ、カナダのゴッド・スピード・ユー・ブラック・エンペラーがロック音楽に弦楽器を本格的な導入を試みて成功し、弦楽奏者をバンド内で演奏させるスタイルが今日においては自然な形として確立された感があります。
レビュー誌などでは上記のバンドが先駆者としてよく挙げられますけれども、知るかぎりにおいて、世界で一番最初に弦楽合奏をロック音楽として取り入れたのは、間違いなくこのオーストラリアの前衛派のバンド、ダーティー・スリーでした。
今作「Whatever You Love,You Are」は、通算二作目となるスタジオ・アルバム。デビュー作「Ocean Songs」に比べ、弦楽のハーモニクスの美麗さが際立ち、楽曲の良さと魅力が分かりやすく引き出されたという理由で、彼等の名作に挙げておきたい。
特にこのアルバムの特異なのは、バイオリンのピチカート奏法の多用を、はじめてロック音楽として取り入れている点。なおかつ、その音楽性というのも、ジプシーが流浪のはての街頭で奏でるような哀愁あるバイオリンのパッセージ、そして、その心細さを支えているのが、ギターのシンプルで飾り気のない質素なアルペジオ、さらに、ドラムのジャズ的なフレージング。これらが組み合うことにより、このバンドの音楽の全体的な音の厚みを形成しています。
このスタジオアルバム「Whatever You Love,You Are」の表向きの楽曲の印象というのは、先にも言ったように、ロック音楽を聴いているというよりか、どこか、異国の街角をあてどなく歩いている際に、ふと、ジプシー民族のリアリティのある流しの演奏が耳にスッと飛び込んでくるような異国情緒があって、そのあたりにはかなげで、淡い哀愁が漂っているように思えます。
ときに、それは、完成された楽曲というより、即興音楽のような雰囲気を持って心にグッと迫ってくるはず。
上品で洗練されたバイオリンを中心とした楽曲の世界は徹底して抑えの効いた雰囲気によって統一され、最初から最後のトラックまで、丹念に音の世界がゆったりと綿密に構成されていく。
そして、このアルバム中、タッチ・アンド・ゴーの四十年という歴史で最も秀逸な楽曲のひとつ、最終トラックにエピローグのような形で有終の美を飾っている「Lullabye for Christie」。
このポスト・ロック屈指の名曲は、全面的な奥行きのある音響世界が、上質で淡い弦楽器のハーモニクスを中心としてミニマルな楽節の構成によって綿密に紡がれる。アンビエントという概念が、今日のミュージックシーンにおいて安売りされすぎている感があるため、ここでは、彼等のクラシック色あふれる良質な楽曲を、そういうふうに呼ぶのを固く禁じておきたい。
最後にひとつ、このダーティー・スリーの名盤を聴かずして、タッチ・アンド・ゴーを素通りすることは出来かねると言っておきます。
・Touch And Go Records Official Site
http://www.tgrec.com/