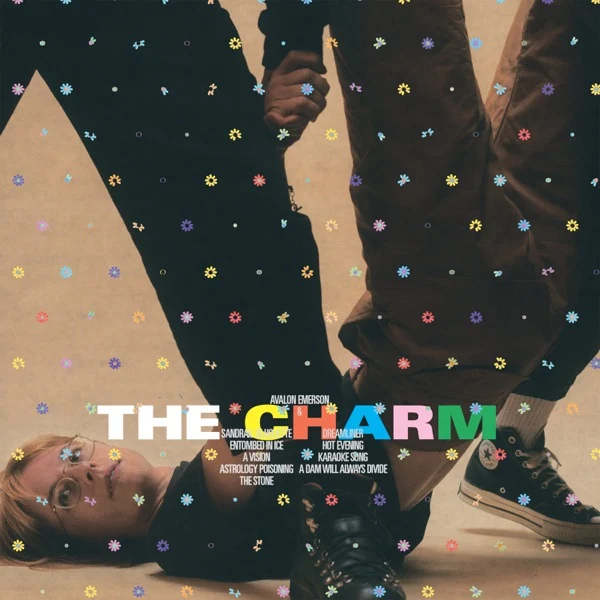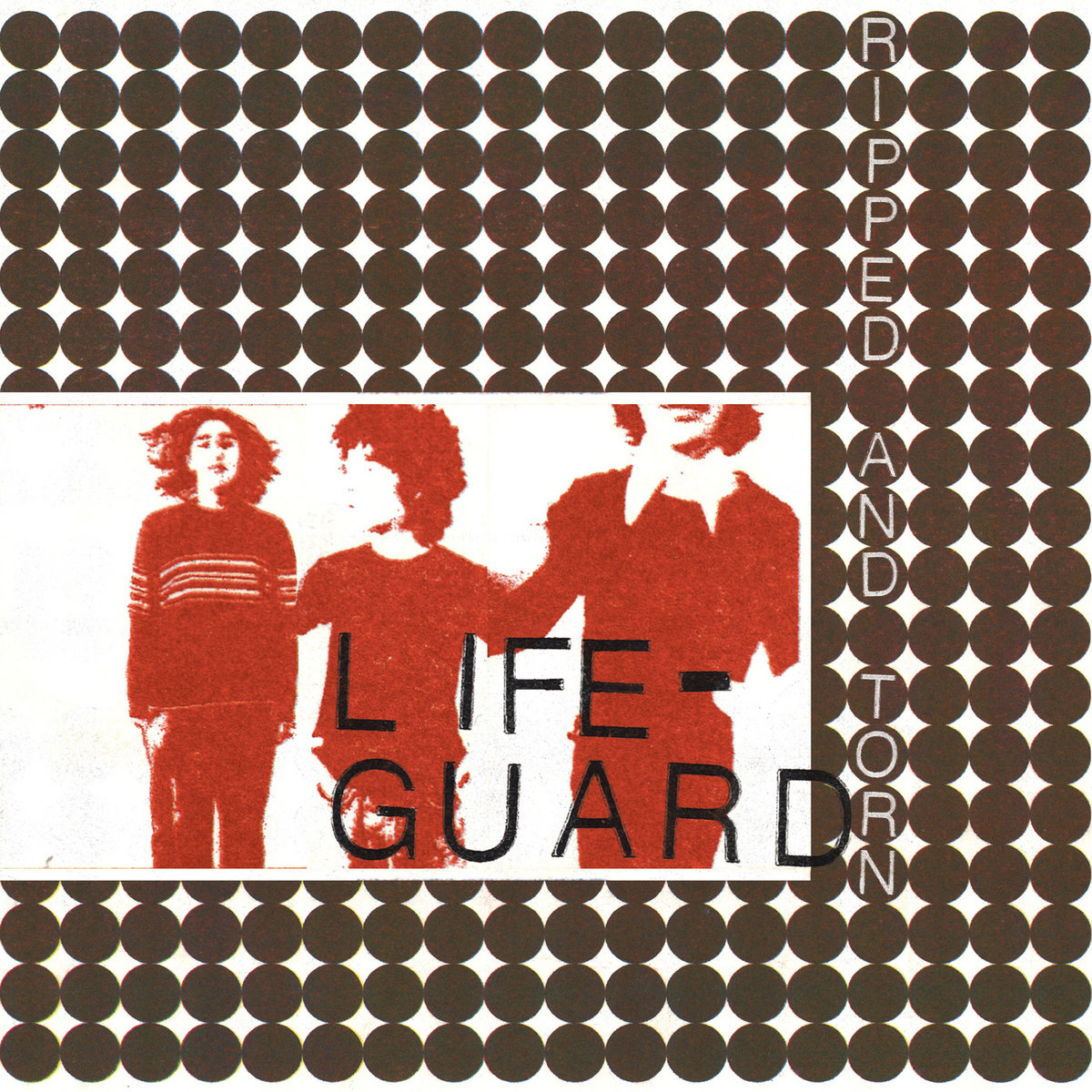|
2010年代のシンセポップ/エレクトロニックポップのミュージック・シーンの席巻から10年を経て、いよいよポップスのクロスオーバーやジャンルレス化が顕著になってきています。
その中で台頭したのが、ベッドルーム・ポップに続いて、ハイパー・ポップ、エクスペリメンタル・ポップという、ワイアードなジャンルです。これらのシーン/ウェイブに属するアーティストは、エレクトロニック、ヒップホップ、メタル、ネオソウル、パンク、コンテンポラリー・クラシカル、ゲーム音楽、それから無数のサブジャンルに至るまですべてを吸収し、それらをモダンなポピュラーミュージックとして昇華させています。2010年代以前のポピュラー音楽と2020年代以降のハイパーポップ/エクスペリメンタルポップの音楽の何が異なるのかについて言及すると、以前は耳障りの良い曲の構成やメロディーを擁するのがポピュラーとしての定義であったが、2020年代以後は必ずしもそうとは言いきれません。ときには、ノイズやアヴァンギャルドミュージックを取り入れ、かなりマニアックな音楽性を選ぶこともあるようです。
特に若い世代にかけて、さらにいえば、流行やファッション性、あるいはデジタルカルチャーに敏感な10代、20代のアーティストにこの傾向が多く見られます。若い年代において広範な音楽的な蓄積を積み重ねることはほとんど不可能であるように思えますが、ご存知の通り、サブスクリプションやストリーミング・サービスの一般的な普及により、リスナーは無数の音楽に以前より簡単にアクセス出来るようになり、それと同時に、自分の好みの音楽を瞬時にアクセス出来るようになったこと(かつての書庫のように膨大な数のレコードのラックを血眼になって探し回る必要はなくなった)、SoundcloudやYoutube、あるいは、TikTokで自らの制作した音楽を気軽にアップロード出来るようになったこと、次いで、それらのアップロード曲に関するリスナーのリアクションが可視化出来るようになったことが非常に大きいように推測されます。
これは、デビュー作をリリースしたばかりのイギリスのシンガー、Pinkpantheressも話している通りで、自分の音楽が大衆にどれくらい受け入れられるのかを推し量る「リトマス試験紙」のようになっています。つまり、こういった手段を取ることにより、ポピュラリティーと自らのマニア性のズレを見誤ることが少なくなった。つまり、多数のリスナーがどういった音楽を必要としているのか、音楽市場の需要がアーティストにも手に取るように分かるようになったのです。もちろん、あえてそのことを熟知した上で、スノビズムを押し出す場合があるにしても……。
そんな中、2023年は女性、あるいはこのジャンルに象徴づけられるノンバイナリーを自称するシンガーソングライターを中心に、これらのハイパーポップのリリースが盛んでした。特にハイパーポップ/エクスペリメンタルポップに属するアーティストに多く見受けられたのが、自らの独自のサブカルチャー性や嗜好性を、それらのポピュラリティーの中に取り入れるというスタイルです。音楽的に言及すれば、メタルのサブジャンルや、エレクトロニックのグリッチを普通に吸収したポップサウンドを提示するようになってきています。これはUKラップなどで普通にグリッチを取り入れることが一般的になっているのと同じように、ポピュラー・ミュージックシーンにもそれらのウェイブが普及しつつあるという動向を捉えることが出来るでしょう。
2023年以降のポピュラー・ミュージックシーン、特に、ハイパーポップというジャンルを見る限りでは、それらの中にどういった独自性を付け加えるのかが今後のこのジャンルの命運を分けるように思われる。
特に今年活躍が目立ったのはアジアにルーツを持つ女性、あるいはノンバイナリーのアーティストだ。必ずしも耳の肥えたリスナー、百戦錬磨のメディア関係者ですら、これらのジャンルの内奥まで理解しているとは言い難いかもしれませんが、少なくともこのジャンルの巻き起こすニューウェイブは、来年移行のミュージックシーンでも強い存在感を示し続けるに違いありません。
今年、登場した注目のハイパーポップ/エクスペリメンタルポップアーティスト、及びその作品を以下にご紹介していきます。
・シンガポール出身のハイパーポップの新星 Yeule ーグリッチサウンドとサブカルチャーの融合ー
Pitchfork Musiic Festivalにも出演経験のあるYeuleは、シンガポール出身のシンガーソングライターであり、現在はLAを拠点に活動している。イエールは、日本のサブカルチャーに強い触発を受けている。
エヴァンゲリオンなどの映像作品の影響、次いで沢尻エリカなどのタレントからの影響と日本のカルチャーに親和性を持っている。加えて、Discordなどのソーシャルメディアの動きを敏感に捉え、自らの活動を、インターネットとリアルな空間を結びつけるための媒体と位置づける。
今年、Ninja Tuneから三作目のアルバム『softcars』を発表し、海外のメディアから高い評価を受けた。ベッドルームポップを基調としたドリーム・ポップ/シューゲイズの甘美なメロディー、そしてボーカルに加え、チップチューン、グリッチを擁するエレクトロニックを加えたサウンドが特徴となっている。もちろん、その音楽性の中にアジアのエキゾチズムを捉えることも難しくない。
「Softcar」ー『Softcar』に収録
・mui zyu ー香港系イギリス人シンガーのもたらす摩訶不思議なエクスペリメンタル・ポップー
 |
香港にルーツを持つイギリスのシンガー、mui zyuは他の移民と同じように、当初、自らの中国のルーツに違和感を覚え、それを恥ずかしいものとさえ捉えていた。ところが、ミュージシャンとしての道を歩み始めると、それらのルーツはむしろ誇るべきものと変化し、また音楽的な興味の源泉ともなったのだった。今年、Mui ZyuはFather/Daughterと契約を交わし、記念すべきアーティストのデビューフルレングス『Rotten Bun For An Eggless Century』(Reviewを読む)を発表した。
ファースト・アルバムを通じ、mui zyuは、パンデミック下のアジア人差別を始めとする社会的な問題にスポットライトを当て、台湾の古い時代の歌謡曲、ゲーム音楽に強い触発を受け、SFと幻想性を織り交ぜたシンセ・ポップを展開させている。他にもアーティストは、中国の古来の楽器、古箏、二胡の演奏をレコーディングの中に導入し、摩訶不思議な世界観を確立している。
「Hotel Mini Soap」ー『Rotten Bun For An Eggless Century』に収録
・Miss Grit ーデジタル化、サイボーグ化する現代社会におけるヒューマニティーの探求ー
 |
デジタル管理社会に順応出来る人々もいれば、それとは対象的に、その動きになんらかの違和感を覚える人もいる。ニューヨークを拠点に活動する韓国系アメリカ人ミュージシャン、マーガレット・ソーンは後者に属し、サイボーグ化しつつある人類、その流れの中でうごめくヒューマニティーをアーティストが得意とするシンセポップ、アートポップの領域で表現しようと試みている。
デビューアルバム『Follow the Cyborg』(Reviewを読む)をMuteから発表。『Follow the Cyborg』でソーンは、機械が、その無力な起源から自覚と解放へと向かう過程を追求している。この作品は、エレクトロニックな実験と刺激的なエレキギターが織り成す音の世界を表現している。ピッチフォークが評したように、「ミス・グリットは、彼女の曲を整然とした予測可能な形に詰め込むことを拒み、その代わりに、のびのびと裂けるように聴かせる」
ミス・グリッツがサイボーグの人生についてのアルバムを構想するきっかけとなったのは、このような機械的な存在のあり方に対する自身の関わりからきている。混血、ノンバイナリーであるソーンは、外界から押しつけられるアイデンティティの限界を頑なに拒否し、流動的で複雑な自己理解を受け入れてきた。ローリング・ストーン誌に「独創的で鋭いシンガー・ソングライター」と賞賛されたMiss Gritのプロセスは内省的で、ビジョンは正確である。ミス・グリッドは、サイボーグの人生を探求する中で、『her 世界でひとつの彼女』、『エクス・マキナ』、『攻殻機動隊』、ジア・トレンティーノのエッセイ(『Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion』より)、ドナ・ホロウェイの『A Cyborg Manifesto』などに触発を受けている。
「Follow The Cyborg」ー『Follow The Cyborg』に収録
Yaeji ーXL Recordingsが送り出す新世代のエレクトロニック・ポップの新星ー
 |
ニューヨーク出身の韓国系エレクトロニックミュージック・プロデューサーであり、DJ、さらにヴォーカリスト、Yaeji(イェジ)は、K-POPのネクスト・ウェイブの象徴的なアーティストに位置づけられる。
2017年のEPリリースをきっかけに世界的に高い評価を受けた後、彼女はチャーリーXCX、デュア・リパ、ロビンのリミックスを手掛け、2回のワールドツアーをソールドアウトさせ、デビュー・ミックステープ・プロジェクト『WHAT WE DREW 우리가 그려왔던』をリリースした。
クイーンズのフラッシングで生まれたイェジのルーツは、ソウル、アトランタ、ロングアイランドに散りばめられている。韓国のインディー・ロックやエレクトロニカ、1990年代後半から2000年代前半のヒップホップやR&Bに影響を受けており、彼女のユニークなハイブリッド・サウンドの背景ともなっている。
『With A Hammer』は、コロナウィルスの大流行による閉鎖期間中に、ニューヨーク、ソウル、ロンドンで2年間にわたって制作された。これは、アーティストの自己探求への日記的な頌歌であり、自分自身の感情と向き合う感覚、勇気を出してそうすることで可能になる変化である。
この場合、Yaejiは、怒りと自分の関係を検証している。これまでの作品とは一線を画している。トリップホップやロックの要素と、慣れ親しんだハウスの影響を受けたスタイルを融合させ、英語と韓国語の両方で、ダークで内省的な歌詞のテーマを扱っている。ヤエジはこのアルバムで初めて生楽器を使用し、生演奏のミュージシャンによるパッチワークのようなアンサンブルを織り交ぜ、彼女自身のギター演奏も取り入れる。「With A Hammer』では、エレクトロニック・プロデューサー、親しいコラボレーターでもあるK WataとEnayetをフィーチャーし、ロンドンのLoraine JamesとボルチモアのNourished by Timeがゲスト・ヴォーカルとして参加している。
「easy breezy」ー『With A Hammer』に収録
yune pinku ーロンドンのクラブカルチャーを吸収した最もコアなエレクトロ・ポップー
 |
現在、サウスロンドン出身のyune pinkuは特異なルーツを持ち、アイルランドとマレーシアの双方のDNAを受け継いでいる。"post-pinkpantheress"とみなしても違和感のないシンガーソングライター。現時点では、シングルのリリースと2022年のEPのリリースを行ったのみで、その全貌は謎めいている部分もある。yuneというのは、子供の頃のニックネームに因み、10代の頃にはビージーズやキンクス、ジョニ・ミッチェルの音楽に薫陶を受けた。若い頃にパンクとインディーズカルチャーに親しみ、その後、ロンドンのクラブカルチャーでファンベースを広げた。
彼女の音楽には、最もコアなロンドンのクラブ・ミュージックの反映があり、そこにはUKガレージ、ダブステップ、 ハウス、ダンスミュージック全般的な実験性を読み解くことが出来る。yune pinkの生み出すエレクトロニック・ポップが斬新である理由は、その音楽に対する目が完全には開かれていないことによる。電子的な音楽を聴くのが楽しくて仕方がないらしく、「まだ電子音楽の異なるジャンルに新しい発見をしている途中なんです」とアーティストは語る。
yuneにとってダンスミュージックはまだ新しく未知なるものなのである。そのため、複数のシングルには電子音楽としてセンセーショナルな輝きに充ちている。今年、発表されたシングル「Heartbeat」は、エレクトロニックのみならず、ポピュラーミュージックとしても先鋭的な響きを持ち合わせている。今後、注目しておきたいアーティスト。
Saya Gray ーCharli XCXのポスト世代に属する前衛的なポピュラー・ミュージックー
 |
今年、Dirty Hitからアルバム『QWERTY』をリリースしたSaya Gray(サヤ・グレー)はトロント生まれ。
アレサ・フランクリン、エラ・フィッツジェラルドとも共演してきたカナダ人トランペット奏者/作曲家/エンジニアのチャーリー・グレイを父に持ち、カナダの音楽学校「Discovery Through the Arts」を設立したマドカ・ムラタを母にもつ音楽一家に育ち、幼い頃から兄のルシアン・グレイとさまざまな楽器を習得した。グレーは10代の頃にバンド活動を始め、ジャマイカのペンテコステ教会でセッションに明け暮れた。その後、ベーシストとして世界中をツアーで回るようになり、ダニエル・シーザーやウィロー・スミスの音楽監督も務めている。
サヤ・グレーの母親は浜松出身の日本人。父はスコットランド系のカナダ人である。典型的な日本人家庭で育ったというシンガーは日本のポップスの影響を受けており、それは前作『19 Masters』でひとまず完成を見た。
デビュー当時の音楽性に関しては、「グランジーなベッドルームポップ」とも称されていたが、二作目となる『QWENTY』では無数の実験音楽の要素がポピュラー・ミュージック下に置かれている。ラップ/ネオソウルのブレイクビーツの手法、ミュージック・コンクレートの影響を交え、エクスペリメンタルポップの領域に歩みを進め、モダンクラシカル/コンテンポラリークラシカルの音楽性も付加されている。かと思えば、その後、Aphex Twin/Squarepusherの作風に象徴づけられる細分化されたドラムンベース/ドリルンベースのビートが反映される場合もある。それはCharli XCXを始めとする現代のポピュラリティの継承の意図も込められているように思える。
曲の中で音楽性そのものが落ち着きなく変化していく点については、海外のメディアからも高評価を受けたハイパーポップの新星、Yves Tumorの1stアルバムの作風を彷彿とさせるものがある。サヤ・グレーの音楽はジャンルの規定を拒絶するかのようであり、クローズ「Or Furikake」ではメタル/ノイズの要素を込めたハイパーポップに転じている。また作風に関しては、極めて広範なジャンルを擁する実験的な作風が主体となっている。一般受けはしないかもしれないが、ポピュラーミュージックシーンに新風を巻き起こしそうなシンガーである。