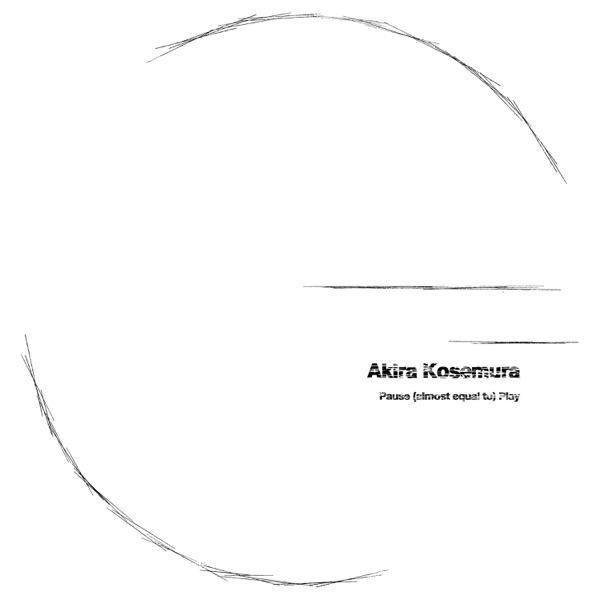坂本慎太郎 「物語のように」
Label: Zelone Records
Release Date: 2022年6月3日、(国内レコード盤は、9月30日から発売)
やはり、日本のインディー界の大御所のリリースがあると、不思議とワクワクするものがある。坂本慎太郎の六年ぶりの新作「物語のように」は、パンデミックを通じて、このアーティストの人生観のようなものを社会情勢を俯瞰して見つめなおすことによって生みだされた作品であるように思える。
坂本さんは、tokionのインタビューで「明るく、フレッシュ、抜けが良い感じにしたかった」と話している通り、アルバムにはそこまで時代背景を象徴したような暗鬱な閉塞感のようなものは見受けられない。ゆら帝時代から一貫しているように、シニカルで、本気なのかどうか定かではないユニークさを交え、坂本慎太郎の一貫した世界がアルバムの底流には通じている。MTRでのデモテープづくりという古いスタイルも、このアルバムのノスタルジアあふれる雰囲気をいや増している。時代観とは距離を置いたまろやかなノスタルジア、それこそが坂本慎太郎さんの魅力であり、その「まったり感」を楽しむための一作であると言えるかもしれない。そして、このアーティストらしい歌詞の独特なニュアンスも健在で、それらは「物語のように」、「それは違法です」、「君には時間がある」といった楽曲に表れている。このシニカルで、ちょっと斜め上を行くかのような、坂本さんの言葉の持つ力が随所にきらりときらめいている。
既に、海外でも豊富なライブ経験、リリース経験がある坂本さんではあるものの、そういった国際意識とは裏腹に、やはり、「英語で歌うという概念は頭になかった」ようです。なぜなら、彼は誰よりも日本語を愛し、その響きを愛する人物だからである。上記のインタビューで話している通り、海外の人にも、音楽性が通じれば、言葉がつながらないという要素は、むしろプラスに転ずると坂本さんは考える。もちろん、それは細野晴臣さんがLAのライブで受け入れられ、既に「ハネムーン」の歌詞が世界の共通語となっていることからもよく分かることかもしれない。
アルバムの音楽性としては、具体的に、このアーティストと指摘するほどの知見を持ち合わせていないものの、 70年代の邦楽ロックに加えて、海外のアーティストの影響を受けて生み出された作品というように見受けられる。それは、ポップス、ハワイアン、サーフ、アフロビート、ファンク、サイケデリック、と、無類の音楽フリークとしての表情を併せ持つ坂本さんらしいサウンドの妙味と相まって、温かく、力みの抜けたグルーヴが作品全体に滲んでいる。これらのサウンドには、音楽を演奏することの喜びにあふれているだけでなく、時代の閉塞感を打破する力が込められている。そして、人生や音楽をより心から楽しむためには、ちょっとした「遊び心」が必要だと教えてくれており、さらに、ときには、人生をこれまでと違った角度から眺めてみることの重要性を教えてくれる。「物語のように」は、日本の正真正銘のインディー・アーティストのキャリアの分岐点であるとともに、彼の最良のアルバムとして挙げても良いのではないか。
Critical Rating:
78/100
・Amazon Link