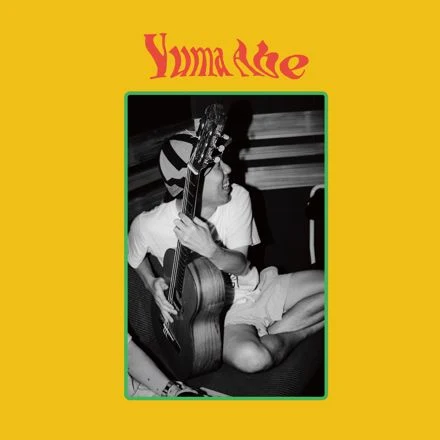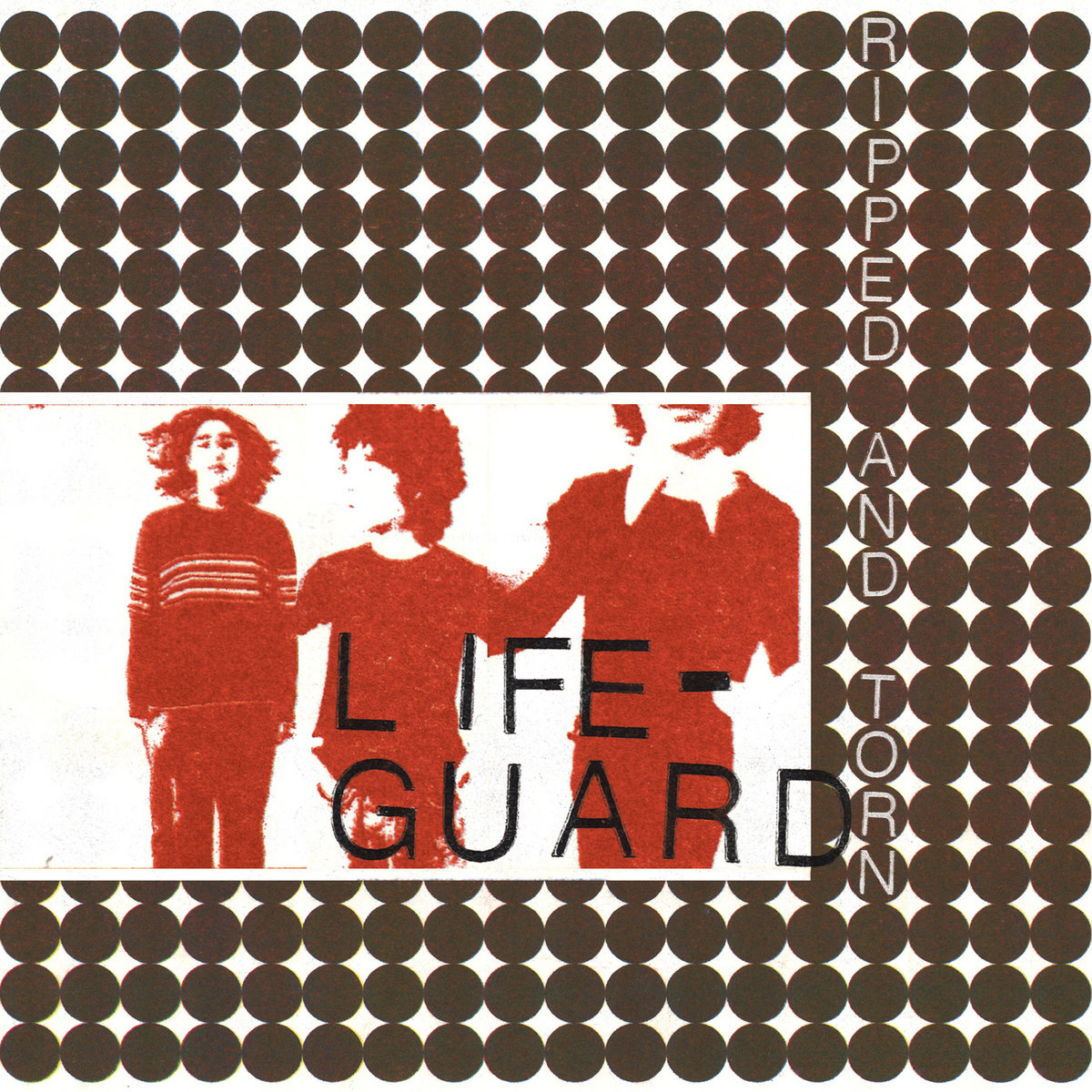Selah Broderick & Peter Broderick
セラ・プロデリックの静謐なスポークンワード、ピーター・ブロデリックがもたらす真善美
ある日、セラ・ブロデリックが、彼女の息子でミュージシャン兼作曲家のピーター・ブロデリックに、「詩を音楽にするのを手伝ってくれない?」と頼んだとき、ピーターは即座に「イエス」と答えた。ピーター・ブロデリックは、セラの美しく傷つきやすい言葉を聴くと、母のこのアルバムの制作を手伝うことに専念したのだ。
『Moon in the Monastery』を構成する8曲は、以後、2、3年かけてゆっくりと着実に作られた。ピーター・ブロデリックの膨大な楽器コレクションと、マルチ・インストゥルメンタリストとしての長年の経験(ヴァイオリン、ピアノ、パーカッションなど)を生かし、ブロデリック親子は試行錯誤のプロセスに着手し、それぞれの詩にふさわしい音楽の音色を辛抱強く探し求めた。
時には、ピーターが母親からフルートを吹いているところを録音してもらい、それをサンプリングの素材にすることもあった。例えば、オープニング曲『The Deer』は、オレゴンの田舎町の丘に日が沈むある晩、野生の鹿との神秘的な出会いを語る彼女の完璧な背景として、サンプリングされ、操作され、彫刻されたセラのフルートだけで構成されている。
ヒーリング・アートに30年以上携わってきたセラの詩は、彼女の職業生活の自然で個人的な延長線上にある。ヨガ、理学療法、マッサージ、ホスピスなど、さまざまな分野で経験を積んだセラは、自身の内面を癒す旅を続けながら、人々の癒しを助けることに人生の多くを捧げてきた。
彼女の文章は、極めて個人的なものから普遍的で親しみやすいものまで、時にはひとつのフレーズで表現される。彼女のペンは、感傷的というより探究心を感じさせる方法で、人間の経験の核心を掘り下げる。
アルバムの中盤、「Faith」という曲の中で彼女はこう言っている。「信仰...それは私の心をとらえ、刻み込み/そして溶けてなくなる/私がその瞬間ごとにそれを更新し続けることを求めそうになる/私がそれを手放し、再びそれを見つけたとき、おそらくそれは深まるのだろうか?」
7曲のスポークン・ワード・トラックの制作を終えたセラとピーターは、アルバムの最後を締めくくる瞑想的なサウンドスケープを作り上げた。
アルバムの8曲目、最後のトラックであるタイトル曲『Moon in the Monastery』は、セラの魅惑的なフルート演奏を再び際立たせ、前の7曲の内容を沈めるための穏やかで夢のような空間を提供している。
Selah Broderick & Peter Broderick 『Moon in the Monastery』/ Self Release
オレゴン州の現代音楽家、ピーター・ブロデリックはこれまで、ロンドンの''Erased Tapes''から良質な音楽をリリースし続けて来た。ピアノによるささやかなポスト・クラシカルをはじめ、くつろいだボーカルトラック、フランスのオーケストラとのコラボレーションを行うなど、その作風は多岐に渡る。ブロデリックの作風は、アンビエント、コンテンポラリー・クラシカル、インディーフォーク、というように1つのジャンルに規定されることはほとんどない。
ニューアルバム『Moon in the Monasteryー修道院の月』は、40分ほどのコンパクトな作品にまとめ上げられている。その内訳は、7つのスポークンワードを基調とするバリエーションと、最後に収録されている20分の静謐で瞑想的な響きを持つ超大なエンディングで構成されている。
記憶に新しいのは、昨年、ピーター・ブロデリックはフランスのオーケストラ、"Ensemble O"と協力し、アーサー・ラッセルのスコアの再構成に取り組んでいる。本作の再構成の目論見というのは、米国のチェロ奏者/現代音楽の作曲家の隠れた魅力に脚光を当てることであったが、と同時に従来のブロデリックのリリースの中でも最も大掛かりな音楽的な試みとなった。
なおかつ、他のミュージシャンやバンドと同じように、1つの経験が別の作品の重要なインスピレーションになる場合がある。実際、このアルバムは、前作の『Give It To The Sky』と制作時期が重なっており、制作を併行して行ったことが、音楽そのものに何らかの働きかけをしたと推測できる。
とくに、ブロデリックは、2分、3分ほどのミニマル・ミュージックを制作してきたのだったが、この数年では、より映画のスコアのように壮大なスケールを持つ作曲も行っている。前作で「ヴァリエーション」の形式に挑戦したことに加え、「Tower Of Meaning X」では、15:31の楽曲制作に取り組んでいる。つまり、変奏曲と長いランタイムを持つ曲をどのようにして自らの持つイマジネーションを駆使して組み上げていくのか、そのヒントはすでに前作で示されていたのだった。
もうひとつ、ピーター・ブロデリックといえば、クラシックのポピュラー版ともいえるポスト・クラシカルというジャンルに新たな風を呼び込んだことで知られている。とくに、彼が以前発表した「Eyes Closed And Traveling」では、教会の尖塔などが持つ高い天井、及び、広い空間のアンビエンスを作風に取り入れ、Max Richterに代表されるピアノによるミニマル・ミュージックに前衛的な音楽性をもたらすことに成功した。これはまた、ロンドンのレーベル”Erased Tapes”の重要な音楽的なプロダクションとなり、ゴシック様式の教会等の建築構造が持つ特殊なアンビエンスを活用したプロダクションは実際、以降のロンドンのボーカルアートを得意とする日本人の音楽家、Hatis Noitの『Aura』(Reviewを読む)というアルバムで最終的な形となった。
『Moon in the Monastery』は、彼の母親との共作であり、瞑想的なセラのスポークンワード、フルートの演奏をもとにして、ピーター・ブロデリックがそれらの音楽的な表現と適合させるように、アンビエント風のシークエンスやパーカッション、ピアノ、バイオリンの演奏を巧みに織り交ぜている。アルバムのプロダクションの基幹をなすのは、セラ・ブロデリックの声とフルートの演奏である。ピーターは、それらを補佐するような形でアンビエント、ミニマル音楽、アフロ・ジャズ、ニュージャズ、エクゾチック・ジャズ、ニューエイジ、民族音楽というようにおどろくほど多種多様な音楽性を散りばめている。例えれば、それは舞台芸術のようでもあり、暗転した舞台に主役が登場し、その主役の語りとともに、その場を演出する音楽が流れていく。主役は一歩たりとも舞台中央から動くことはないが、しかし、まわりを取り巻く音楽によって、着実にその物語は変化し、そして流れていき、別の異なるシーンを呼び覚ます。
主役は、セラ・ブロデリックの声であり、そして彼女の紡ぐ物語にあることは疑いを入れる余地がないけれど、セラのナラティヴな試みは、飽くまで音楽の端緒にすぎず、ピーターはそれらの物語を発展させるプロデューサーのごとき役割を果たしている。
プレスリリースで説明されている通り、セラは、「オレゴンの田舎町の丘に日が沈むある晩、野生の鹿との神秘的な出会い」というシーンを、スポークンワードという形で紡ぐ。声のトーンは一定であり、昂じることもなければ、打ち沈むこともない。ある意味では、語られるものに対してきわめて従属的な役割を担いながら、言葉の持つ力によって、一連の物語を淡々と紡いでいくのだ。
シャーウッド・アンダソンの『ワインズバーグ・オハイオ』の米国の良き時代への懐古的なロマンチズムなのか、それとも、『ベルリン 天使の詩』で知られるペーター・ハントケの『反復』における旧ユーゴスラビア時代のスロヴェニアの感覚的な回想の手法に基づくスポークンワードなのか、はたまた、アーノルト・シェーンベルクの「グレの歌」の原始的なミュージカルにも似た前衛性なのか。いずれにしても、それは語られる対象物に関しての多大なる敬意が含まれ、それはまた、自己という得難い存在と相対する様々な現象に対する深い尊崇の念が抱かれていることに気がつく。
当初、セラ・ブロデリックは、オレゴンの、のどかな町並み、自然の景物が持つ神秘、動物との出会いといったものに意識を向けるが、それらの言葉の流れは、必ずしも、現象的な事物に即した詩にとどまることはない。日が、一日、そしてまた、一日と過ぎていくごとに、外的な現象に即しながら、内面の感覚が徐々に変化していく様子を「詩」という形で、克明にとどめている。
セラ・ブロデリックの内的な観察は真実である。それは、自然や事実に即しているともいうべきか、自分の感情に逆らわず、いつも忠実であるべく試みる。彼女は明るい正の感覚から、それとは正反対に、目をそむけたくなるような内面の負の感覚の微細な揺れ動きを、言葉としてアウトプットする。
その感覚は驚くほど明晰であり、感情を言葉にした記録のようであり、それとともに、現代詩やラップのような意味を帯びる瞬間もある。内的な感情が、刻一刻と変遷していく様子がスポークンワードから如実に伝わってくる。そして、それらの言葉、物語、感情の記録を引き立て芸術的な高みに引き上げているのが、他でもない、彼女の息子のピーター・ブロデリックである。彼は、アンビエントを基調とするシンセのシークエンスを母の声の背後に配置し、それらの枠組みを念入りに作り上げた上で、巧みなフルートの演奏を変幻自在に散りばめている。サンプリングの手法が取り入れられているのか、それとも、リアルタイムのレコーディングがおこなわれているのかまでは定かではないが、言葉と音楽は驚くほどスムーズに、緩やかに過ぎ去っていく。
ピーター・ブロデリックの作風としてはきわめて珍しいことであるが、アルバムの序盤の収録曲「I Am」では、民族音楽の影響が反映されている。
一例としては、''Gondwana Records''を主催するマンチェスターのトランペット奏者、Matthew Halsall(マシュー・ハルソール)が最新アルバム『An Ever Changing View』において示した、民族音楽とジャズの融合を、最終的にIDM(エレクトロニック)と結びつけた試みに近いものがある。
アフリカのカリンバの打楽器の色彩的な音階を散りばめることにより、当初、オレゴンの丘で始まったと思われる舞台がすぐさま立ち消えて、それとは全然別の見知らぬ土地に移ろい変わったような錯覚を覚える。
そして、カリンバの打楽器的な音響効果を与えることにより、セラ・ブロデリックのスポークンワードは、力強さと説得力を帯びる。それは、ニューエイジやヒーリングの範疇にある音楽手法とも取れるだろうし、ニュージャズやエキゾチック・ジャズの延長線上にある新しい試みであるとも解せる。
少なくとも、ジャンルの中に収めるという考えはおろか、クロスオーバーという考えすら制作者の念頭にないように思えるが、それこそが本作の音楽を面白くしている要因でもある。その他にも旧来のブロデリックが得意とするアンビエントの手法は、序盤の収録曲で、コンテンポラリー・クラシック/ポスト・クラシカルという制作者のもうひとつの主要な音楽性と合致している。
ピーター・ブロデリックは、バイオリンのサンプリング/プリセットを元にして、縦方向でもなく、横方向でもない、斜めの方向の音符を重層的に散りばめながら、イタリアのバロックや中世ヨーロッパの宗教音楽をはじめとする「祈りの音楽」に頻々に見受けられる「敬虔な響き」を探求しようとしている。上記のヨーロッパの教会音楽は、押し並べて、演奏者の上に「崇高な神を置く」という考えに基づいているが、不思議なことに、「Mother」において、セラ・ブロデリックの語りの上を行くように、ヴァイオリンの響きがカウンターポイントの流れを緻密に構築しているのである。
同じように、Matthew Halsall(マシュー・ハルソール)が最新作で示したようなアフロジャズとオーガニックな響きを持つIDMの融合は、続く「Faith」にも見出すことができる。ここではセラのトランペットのような芳醇な響きを持つフルートの演奏、ジャズ的な音楽の影響を与えるスポークンワード、シンセのプリセットによるバイオリンのレガート、さらに、奥行きを感じさせるくつろいだアンビエントのシークエンスという、複合的な要素が綿密に折り重なることで、モダン・ラップのようなスタイリッシュな響きを持ち合わせることもある。
シンセのシークエンスが徐々にフルートの演奏を引き立てるかのように、雰囲気や空気感を巧みに演出し、次いで、最終的にはセラ・ブロデリックの伸びやかなフルートの演奏が音像の向こうに、ぼうっと浮かび上がてくる。アフロ・ジャズを基調とした彼女の演奏が神妙でミステリアスな響きを持つことは言うまでもないが、どころか、アウトロにかけて現実的な空間とは異なる何かしら神秘的な領域がその向こうからおぼろげに立ち上ってくるような感覚すらある。
アルバムの序盤は温和な響きを持つ音楽が主要な作風となっているが、中盤ではそれとは対象的に、Jan Garbarek(ヤン・ガルバレク)の名曲「Rites」を思わせるような独特なテンションを持つ音楽が展開される。
続く「Cut」では、映画音楽のオリジナルスコアの手法を用い、緊張感のある独特なアンビエンスを呼び覚ます。イントロのセンテンスが放たれるやいなや、空間の雰囲気はダークな緊迫感を帯びる。それは形而上の内的な痛みをひとつの起点にし、スポークンワードが流れていくごとに、自らの得がたい心の痛みの源泉へと迫ろうという、フロイト、ユング的な心理学上の試みとも解せる。それらはピーターによるノイズ、ドローン的なアルバムの序盤の収録曲とは全く対蹠的に、内的な歪みや亀裂、軋轢を表したかのような鋭いシークエンスによって強調される。
Tim Hecker(ティム・ヘッカー)が『No Highs』(Reviewを読む)で示した「ダーク・ドローン」とも称すべき音楽の流れの上をセラ・ブロデリックの声が宙を舞い、その着地点を見失うかのように、どこかに跡形もなく消え果てる。そして、それらのドローンによる持続音が最も緊張感を帯びた瞬間、突如そのノイズは立ち消えてしまい、無音の空白の空間が出現する。そして、急転直下の曲展開は、続く「静寂」の導入部分、イントロダクション代わりとなっている。
「Silence」では、対象的に、神秘的なサウンドスケープが立ち上る。アンビエントの範疇にある曲であるが、セラの声は、旧来のアンビエントの最も前衛的な側面を表し、なおかつこの音楽の源泉に迫ろうとしている。2つの方向からのアプローチによる音楽がそのもの以上の崇高さがあり、心に潤いや癒やしをもたらす瞬間すらあるのは、セラ・ブロデリックの詩が自然に対する敬意に充ちていて、また、その中には感謝の念が余すところなく示されているからである。
続く「True Voice」では、精妙な感覚が立ち上り、声の表現を介して、その感覚がしばらく維持される。ピーター・ブロデリックの旧来のミニマリズムに根ざしたピアノの倍音を生かした演奏が曲の表情や印象を美麗にしている。これは『Das Bach Der Klange』において、現代音楽家のHerbert Henck(ヘルベルト・ヘンク)がもたらしたミニマル・ピアノの影響下にある演奏法ーー短い楽節の反復による倍音の強化ーーの範疇にある音楽手法と言えるかもしれない。
20分以上に及ぶ、アルバムのクローズ曲「Moon in the Monasteryー修道院の月」は、ニューエイジ/アンビエントの延長線上にある音楽的な手法が用いられている。一見すると、この曲は、さほど前衛的な試みではないように思える。しかし、ブロデリックは、パーカションの倍音の響きの前衛性を追求することで、終曲を単なる贋造物ではない、唯一無二の作風たらしめている。
その内側に、チベット、中近東の祈りが込められていることは、チベット・ボウル等の特殊な打楽器が取り入れられることを見れば瞭然である。なおかつ、クローズ曲は、ドローン・アンビエントの範疇にある、現代音楽/実験音楽としての最新の試みがなされていると推察される。しかし、その響きの中には真心があり、豊かな感情性が含まれている。取りも直さずそれは、音楽に対する畏敬なのであり、自然や文化全般、自らを取り巻く万物に対する敬意にほかならない。これらの他の事物に対する畏れの念は、最終的には、感謝や愛という、人間が持ちうる最高の美へと転化される。
音楽とは、そもそも内的な感情の表出にほかならないが、驚くべきことに、これらは先週紹介したPACKSとほとんど同じように、「平均的な空間以上の場所」に聞き手を導く力を具えている。抽象的なアンビエント、フルート、スポークンワード、鳥の声、ベル/パーカッションの倍音、微分音が重層的に連なる中、タイトルが示す通り、幻想的な情景がどこからともなく立ち上がってくる。その幻惑の先には、音楽そのものが持つ、最も神秘的で崇高な瞬間がもたらされる。それは一貫して、教会のミサの賛美歌のパイプ・オルガンのような響きを持つ、20分に及ぶ通奏低音と持続音の神聖な響きにより導かれる。極限まで引き伸ばされる重厚な持続音は、最終的に、単なる幻想や幻惑の領域を超越し、やがて「真善美」と呼ばれる宇宙の調和に到達する。
95/100
Selah Broderick & Peter Broderick 『Moon in the Monastery』は自主制作盤として発売中です。アルバムのご購入は
こちら。
先週のWeekly Music Featureは以下よりお読みください:
以下の記事もあわせてお読み下さい:
EXPERIMENTAL MUSIC : 2023: 今年の実験音楽の注目作 BEST 10